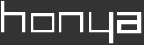ポテトサラダ通信 69
映画Perfect Daysについて
校條剛
前回に続いて「フェイスブックの渡辺隆司君・その2」を書くつもりでしたが、準備が整わないので次回に伸ばし、先日観た映画「パーフェクト・デイズ」についての感想を述べることにしたいと思います。
この映画の監督ヴィム・ヴェンダースの作品はこれまで何本か観ていて、好きな監督の一人です。「パリス、テキサス」「ベルリン・天使の詩」「東京画」「ハメット」「ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ」。このうち、「パリス、テキサス」は日本では「パリ、テキサス」と表記されることが多いのですが、パリスはテキサスにある田舎町の名前であり、フランスのパリを指しているのではありません。地名の由来がフランスのパリであるでしょうし、また綴りも同じで「Paris」ですがまったく別の英語圏の土地なのです。しかも、「s(ス)」という文字で韻を踏んでいるわけですから、「パリ、テキサス」ではタイトルにこめられた「音」の良さがぶち壊しになってしまいます。文句ついでに述べますと、Wikipediaでは、ヴェンダースの主な作品というタイトルの並びに、私が観た「ハメット」と「東京画」は入っていません。Wikiであれば、全作品を網羅するべきでしょう。
初めから文句たらたらですが、実は今回の「Perfect Days」にも文句たらたらなのです。そもそも、観なくてもいいと考えていたこの作品のために映画館に足を運ぶ気持ちになったのは、フェイスブックの「友達」の一人が特別な感動の言葉を綴っていたからです。その人は映画も絵画もよくご覧になるご仁なので、コンテンツを判断する目が肥えていると考える根拠がありました。私の評価はかなり低かったわけですから、ひとそれぞれ感性が違っているのだとあらためて知らされた次第です。
さて、この映画のどこが私の感性では不満足だったのかを話しましょう。
大きく分けると以下の二点になります。
1.アイコンの安易さ
2.エピソードの通俗
まずは、アイコンについてです。
アイコン;カセットテープ、木賃アパート、駅地下道の居酒屋、風呂屋、文庫本(古本屋)、お気に入りの一本の樹木、場末のスナック。
これらのアイコンには共通の性質が見られます。「滅びかかっているもの」「忘れられかかっているもの」という性質です。家出してきた姪と一緒に自転車で走る川の風景もアイコンの一つに数えてもいいのですが、これはモノではないので、ここでは一応外します。
これらのどこが安易であり、また安易な選択どうして良くないことなのかを説明しましょう。
安易さとは、言葉通りすぐに思い浮かべるようなありふれた設定と言っていいでしょう。トイレ掃除を生業として暮らしている独身の初老の男を取り巻く住と食の環境として、木賃アパートや扉のない駅地下通路の居酒屋は最初に思い浮かぶシチュエイションでしょう。
居酒屋では約束通りにチューハイを飲んでいます。居酒屋に行く前だか後だか忘れましたが、風呂もシャワーもない木賃アパートですから、銭湯に通うことになりますが、実はお風呂に入るのに、大人500円が必要ですから、自宅でシャワーを浴びるほうが安くあがります。映画の主人公は一見、地味な生活ぶりに見えますが、仕事に使う軽自動車を所持し(アパートの前に駐車していますが、これも都心では何万円もとられますよ)、毎日銭湯に入り、居酒屋とスナックに通ったりしていれば、かなり贅沢な資金が必要でしょう。まあ、スナックは一週間に一度とかかもしれませんし、趣味が読書となると、安く済みますが、主人公がひと月いくらの予算で生活しているのか、しっかりと計算しているとは思えません。監督が自分の好きなアイコンを集めたらこうなったということなのでしょう。なかではカセットテープで「朝日のあたる家」を使っているのだけは、グッドでした。
監督の趣味は文庫本の選択にも行き渡っていて、パトリシア・ハイスミスの短編集を主人公に読ませて、ハイスミスへの賛辞を喋らせていますが、ヴェンダースはハイスミス原作の「アメリカの友人」を映画化しているのです。それが悪いとは言えませんし、幸田文の文庫も褒めそやしているので、バランスをとってはいますが、「なんだかなあ」という言葉が漏れ出てしまいます。
古い日本の道具ばかり集めているのです。監督は小津信者ですから、気持は分かりますが、逆に小津映画を観ていると、古きを懐かしがるなんてことをしていないことに気づかされます。小津は現代を描いていたのです。
次にエピソードの通俗性について語りましょう。
エピソードは大きく分けて、三つでしょうか。
一つ目はトイレ掃除の若い相棒とガールズバーの女の子との恋愛、二つ目は姪の家出、三つ目は行きつけのスナックのママの元夫の癌病告白。
いずれのエピソードも、ほとんど「匂わせ」で終わっています。主人公は社会の上澄みのなかで生きていて他人と深く関わることをしないので、一見OKに思えますが、ドラマに入り込まず、表面の露出部分を撫でるだけなので、それぞれのエピソードの感銘が伝わってきません。
例えば、姪の家出を取り上げてみましょう。姪がどういう理由で家出をしてきたのかは、詳しく語られません。そして、母親が迎えにきたときにあっさりと諦めて戻っていきます。この姪がトイレ掃除を生業としている伯父に何を期待していたのか、あいまいな気分しか伝えられません。この家出の独自性はどこにあるのでしょう? よくある家出のエピソードなのですが、誰にも独自な形があるはずなのに、それがまったく語られないのです。
ガールズバーの女の子と主人公の相棒(若い男)との恋愛にしても、監督は特異なケースとして描いているつもりでしょうが、ありふれた内容です。
スナックのママの元亭主の告白(癌で余命の宣告)も同様、きわめてありふれたエピソードとしか感じられません。観客に与えられた情報が少なすぎるのですが、表現者が往々にして間違えるのは、氷山の露出部分だけを知らせておけば、あとは観客が想像できるだろうと期待してしまうことです。それは間違った考えだと私は思っています。
ヴェンダースは小津へのリスペクトを映像で表現したかったのでしょうが、その思いにとらわれ過ぎて、失敗したのだと私は考えます。
小津映画は黒沢映画と比較して、日常の小さなドラマをあくまでも波立たせずに描いているのだとヴェンダースが考えているのだとしたら、まことに残念なことです。