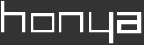ポテトサラダ通信 64
平岩弓枝先生への詫び状
校條剛
訃報が届いたのは、2023年の6月20日のことだったでしょうか。すでに16日には亡くなられていたとかで、お葬式はご家族だけで済ませられたと報道で知りました。ご体調思わしくないとは伺っておりましたが、まだまだお会いするチャンスはあるだろうと思っていました。その機会があれば、もろもろのことお詫びを申し上げたいと密かに考えていました。
実は四年まえの2019年7月、「播州酒・食・文化懇話会」主催の「播州の酒・江戸の宴」(明治記念館)に出席した際に、懇話会の川西千秋さんから「平岩先生がいらっしゃるので、同じテーブル席を用意しました」とありがたいお言葉に当日を楽しみにしていました。不安混じりながら十七年ぶりでお会いできるわけです。私が京都の芸大に常勤の教授として赴任している間の2017年にはお出でになられたとのこと、期待は十分根拠がありました。しかし、その年にはなぜか先生のお姿は見られず、用意された席は空いたままでした。体調不良というより、単にお忘れになってしまっていたことのようです。しかし、あの物事をあいまいにすることをお嫌いだった先生がお忘れになるはずはなく、すでに記憶力が衰えてらしたのかもしれません。
2017年に私が東京にいればよかったのですが、人使いの荒い京都の芸大では、特に7月は土日もオープンキャンパスが入り、一日の休みもないほどにこき使われていましたので、2019年春に大学を退いてからやっと余裕が出来たのです。私が新潮社の文芸部門から離れたときから始まった、こうした行き違いが最後まで平岩先生との距離を遠ざけてしまったようです。
姫路の酒蔵を中心にしたグループの「播州酒・食・文化懇話会」との縁は、平岩先生が付けてくださったものでした。そもそもは、播州赤穂の大石内蔵助の妻りくの生涯を描いた『花影の花』の版元が新潮社だというので、文庫の担当者が平岩先生と姫路に行きませんかと誘ってきたことが始めだったと記憶します。
私は雑誌「小説新潮」に二十年いて、そのとき編集長になっていましたが、平岩先生を担当したことはなく、それどころかお会いしたこともありませんでしたので、最初から編集長としてお付き合いが始まったことになります。
「小説新潮」の若い編集者だったころは、平岩先生の小説は現代ものが主流で、生涯書き継いだ「御宿かわせみ」のシリーズは「小説サンデー毎日」誌の連載として始まったばかり、発表誌が「オール読物」に移ってからの、後年の人気は誰も想像ができなかったことでしょう。「小説新潮」の先生の担当者は田中武次郎さんという五十年配の男性で、編集者というより、どこぞの中学の教頭さんかと思える外見の方でした。二、三年に一度、平岩先生の連作シリーズ企画を会議で通してはいましたが、編集部としては雑誌の売り物になる作家とは考えていなかった時期だったでしょうか。
私の記憶にある限り、田中さんの担当した連作シリーズは(単発作品はなかったと思います)すべて現代ものシリーズで『風子』とか『花ホテル』とかのタイトルで書籍化されました。
新潮社での単行本デビューは、その『風子』あたりが最初だったのではないでしょうか。先生は、若いころから大衆文学の大家長谷川伸の門下生になり、師の教えは一から十まで守ろうとする忠実さで修業に励んだので、師の可愛がり方も尋常ではなかったようです。先生は終生長谷川伸の教えを忘れないで、ことあるごとに師の言葉を引用し、講演会でも「私の恩師の長谷川先生は」という一節が必ず登場したものです。
『花影の花 大石内蔵助の妻』は現在、文春文庫に引っ越しをしているようですが、もとは新潮社で1990年に単行本が刊行されたのです。「小説新潮」での連載ではなかったので、地方新聞か週刊誌の連載を単行本のときにもらったのでしょうか。その経緯を知らないのは、平岩番としては情けがないところですが、新潮社との縁が深くなったのは、この作品がきっかけなのです。版元が新潮社であったことで、平岩先生は、播州関係は新潮社の人間が関わるのがいいと判断されたようでした。当時文庫編集部にいた森正さんという女性が、私に話を持ってきたのだとこうして書いているうちに思い出しました。
平岩先生が播州の方々(主に姫路)と親しくなられたのは、『花影の花』で赤穂を取材しただけではなく、高砂市の酒商川西さん(前出の方です)とのワインを味わうドイツの旅で意気投合して、旅行後も交友が続いたという理由もありました。
播州の中心地姫路市との縁も深くなり、毎年十月下旬に開かれる恒例の「播州酒・食・文化懇話会」のまえ、その日の昼間に市民ホールで講演をするのが決まりのようになりました。我々新潮社勢もこの講演から参加することが慣例となって、講演後は市長室で市長と先生の懇談にも同席していました。先生の講演は、まるで小説のストーリーのようで、起承転結が整った見事な「作品」でした。天性のストーリー・テラーというだけではなく、あらかじめ話の構成が城壁のように堅固に組み立てられているという印象を受けました。これくらいの技術を持つのが「プロ」であるという意味を聴いている編集者たちにも分かってほしかったのでしょう。「プロ」の在り方という点に関して、平岩先生は厳しい意見を常に語られていました。
「播州酒・食・文化懇話会」は春三月と秋十月の年間二回開かれていましたが、我々新潮社の編集者たちが参加するのは、秋の会と決まっていました。会場は新幹線姫路駅前のホテル・サンガーデン姫路(現在は「ホテル日航姫路」に変わっています)でした。
私が「小説新潮」の編集部を去る前年あたりから新潮社だけではなく、文藝春秋の「オール讀物」からも参加者が出るようになっていましたが、平岩先生が私を頼りにしてくださっていたのは確かだと思いますし、新潮社の文芸部門にずっと留まって、自分との友好関係が続くものとお考えになっていらしたことは確かでしょう。私が先生と親しくなってから、「小説新潮」では他誌では書けない新開拓の意欲作を発表してくださいましたし、新潮社での書籍化もそれまでの何倍か増えたことが私との関係を証明しています。
姫路の会が終わった翌日、先生にご馳走になることもまた恒例行事でした。書寫山(しょしゃざん)の塔頭 壽量院(たっちゅう じゅりょういん)の精進料理、神戸北野「ジャン・ムーラン」のフレンチ、「大阪吉兆」の懐石料理、川西さんたち播州懇の皆さんを同道しての岐阜長良川畔「潜龍」の牛肉料理などその日その日の情景がたちまち蘇ってきます。
2002年末をもって、二十九年間在籍した「小説新潮」を離れるとき、しばらくは社内に行き場所がないことを平岩先生にご説明し、しかし「このままで終わるつもりはありませんから、ご心配なきように」と申し上げたのですが、その後とうとう文芸への復帰はないままに定年を迎えてしまいました。
私自身は文芸を離れ、社内出世からも遠ざかることで、かえって自力を蓄えて、物書きとして、また教育者として独り立ちが可能になったのですが、伴走してくれる編集者として考えていただいていたはずの平岩先生の期待を大いに損ねることになってしまいました。
作家にとって、自分に伴走してくれる編集者ほどありがたいものはないと作家になった今、理解しています。まして、編集長クラスの編集者がそばについているというのは、作家にとって一生ものの財産なのに、せっかく交際を重ね(お金も使っていただきました)、お互いに肝胆相照らす仲となった途端に姿を消されたのではたまりませんですよね。「あの人の存在はいったい何だったのだろうか」と亡くなられるまで、先生の中では疑問として残っていたのではないだろうかと想像すると、2019年に「江戸の宴」でお会いできなかったことがことさらに残念でなりません。
平岩先生、いろいろ本当にありがとうございました。安らかにお休みください。