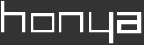ポテトサラダ通信 57
小説作法の殺人
免条剛(校條剛改め)
おそらく10月13日(木)には、私の初めての小説作品『小説作法の殺人』(祥伝社)全国の主要書店の店頭に並んだことと思います。部数が多くはないので(増刷で部数を増やしたい)、首都圏か大都市の大書店でしか手に入らないかもしれませんが、その場合にはネット通販でお願いします。
定価は税込で1870円です。400ページに近いヴォリュームですから、この値付けは致し方ないでしょう。電子版も同時発売になっています。
そして、小説家としての出発を機にペンネーム「免条剛(めんじょう・ごう)」を使うことにしました。といっても、本名の「校條剛」も読みは「めんじょう・つよし」なので、音としてはほとんど変化がありません。なぜ、ペンネームを本名とはまったく別のものにしなかったのかというと、現在72歳の私が「めんじょう」以外の名前で呼びかけられても、振り向くことが困難であろうと想像されたからです(笑)。
というわけで、今後はエッセイも含めて、ネームは免条を使いたいと考えています。
さて、私は、これまで数冊の書籍を上梓しています。大きく分けて、一つは「作家の評伝」、もう一つは「小説の書き方」本です。
その「小説の書き方」本のうち単独で書いたのが『スーパー編集長のシステム小説術』(ポプラ社)という一冊です。
誰が「スーパー編集長」なんだと今は恥ずかしい気持ち一杯ですから、現在、著者紹介の略歴でも省くことが多い書籍ですが、実はこうした「実用書」は、作家の評伝などよりずっと商売になります。この本も二回ほど増刷しているのではなかったでしょうか。帯に「小説は誰にでも書ける!」とデカ文字で謳っているのも、売れ行きがよかった理由かもしれません。「システム」として小説を捉えたところがいいと褒めてくれた人もいました。
それはともかく、「小説は誰にでも書ける」と強調したのなら責任を取れ! という声がずっと聞こえていました。要するに、お前も書いてみろ! ということなのです。お前が書けないのなら、この本(システム小説術)は、ウソ八百本になっちゃうぞというわけです。
もっとも、そんなことでケチを付けて責めてくる読者はおらず、ひたすら自らが背負ったつもりの十字架だったのですけれど。
会社の定年後も糖尿病になったり、京都の芸大に勤めるために、単身赴任していたり、その傍ら作家の評伝を書いたりと、小説に挑戦する余裕がありませんでした。
ということで、歳月は流れ、やっと70歳近くになって、今回の小説の第一稿が完成しました。まだ六十代のうちだったと記憶します。それから、二年以上の間は編集者や編集者OBの知り合いに読んでもらっては、書き直しの日々です。どれくらい削ったり加えたりしたか、記録をとってはいませんが、二年間は推敲というより、ほとんど書き直しばかりしていたと言っても差し支えないでしょう。
そして、72歳の春、祥伝社の編集者二人が「OK」の判定をしてくれたというわけです。
タイトルでお分かりかと思いますが、この小説のジャンルはミステリーです。若い頃はミステリーを書くことになるとは想像もしていませんでしたが、人生先々のことは「今」の時点では予測できないものです。
新潮社に入社して、エンタメ小説の雑誌「小説新潮」に配属され、一夕先輩編集者から誘われて、酒を飲んだときのこと。「自分はほとんどのジャンルの小説は担当できますが、ミステリーだけは苦手ですから、勘弁してください」と23歳の口から確かにその言葉が出たのですが、舌の根がすっかり乾いた72歳の私はミステリーを書いていたというわけ。
そんなものなんですね。
『小説作法の殺人』をすでに読んでいただいた有力書店員から、「昭和の雰囲気」という感想をもらいました。そういえば、第一稿を読んで意見を書きだしてくれた編集者からは「80年代風という印象」と。つまり、ファンタジーやホラー仕様になっている現代日本のミステリーと比べると、古風な感じを受けるのかもしれません。しかし、二人とも否定的な意味合いではなかったようです。私としては、現今の日本のミステリー(「特殊設定」ものなど)と対抗するつもりはなく、リアリズムが基調の海外の作品と釣り合いが取れればいいと考えています。今後も古今の海外ミステリーを視野に入れて書いていくつもりなのです。
私は長いこと小説教室や大学で「小説作法」を教えてきましたが、いくつもある作法の一つに「不得意分野には足を踏み入れないこと」という一条を設けていました。
ミステリーのジャンル内でも、苦手な「暗号」「密室」「特殊設定(論理無視の設定)」などには手を出さないようにしています。
元光文社の役員で私と同年のY氏が、読んでくれたあとに感想の葉書をくれました。「校條さんの小説力に乾杯!」。嬉しかったですね。
小説家は、褒め言葉しか聞きたくないんです。