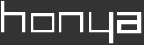ポテトサラダ通信 50
オペラは好きですか?
校條 剛
数年まえのことですが、大阪曾根崎のビアホール「ニューミュンヘン本店」で「オペラ」を巡って、言い争いになったことがありました。相手は、私より十歳以上年少の友人Aで、私が編集長を務めた小説雑誌の新人賞を二十年以上まえに取った作家でした。
私よりも遙かにクラシック音楽への造詣は深く、演奏会に出掛ける回数も多く、関西地区の大阪、神戸はもとより名古屋あたりにまで、遠征して聴きに行っているようでした。
私はめったにコンサートへは行きません。来日した有名なオーケストラやオペラの公演のチケットが一万円だとして、そのお金で買えるCDの枚数を数えてしまうからです。
日本のオーケストラでももちろんいいのですが、チケットを取る手間が限りなく面倒だと思ってしまいます。オペラに関していうと、日本人だけで外国のオペラを演じる場合は、いわゆる「赤毛もの」になるわけですが、生理的にこれは受けつけないのです。劇団四季のミュージカルを見に行かないわけも同様の理由からです。
そういう私をAがコンサートに誘ってくれるようになりました。私の分も券を押さえてくれて、一緒に実演を聴くというようなことが年に二回ほどありました。私が出版社の定年を迎えた数年後に京都の芸大の教授になり、京都に単身赴任したので、大阪に住んでいるAとの距離が近くなり、関西地区の演奏会に出向くことが容易くなったためでした。
最後の同行になったコンサートは、確か「炎の」小林研一郎指揮の「第九」でした。オーケストラが超一流でなかったせいもあるのか、燃え上がるような熱演を期待したのが肩すかしを食らった感がありましたが、まあ格段の不満はありませんでした。
例によって、曾根崎新地の「ニューミュンヘン」へ二人で寄ります。生ビールの大ジョッキ、この店の名物の笠を広げたキノコのような唐揚をまず注文。
二人ともかなり出来上がってきたときに、私はそのころ読んでいた本のなかのエピソードを話しました。指揮者の小澤征爾に作家の村上春樹が質問する形で小澤の音楽観や履歴が述べられる分厚い本です。
そのなかで、小澤が「カラヤン先生」と呼ぶ大指揮者カラヤンの言葉が紹介されます。大体、次のようなことでした。
「ワーグナーをやりたいのなら、オペラを手がけるしかないよ。ワーグナーはオペラでしか分からないじゃないか」と。だから、君もワーグナーのオペラ作品に取り組まないと駄目だと。
*ワーグナーの後期作品は、レチタティーヴォとアリアの区別がない「無限旋律」なので、オペラではなく、正確には楽劇(ムジーク・ドラマ)というジャンルになりますが、本稿ではそこまで厳密には規定しません。
日本のクラシックファンのなかにも、ワーグナーは序曲・前奏曲集という声楽の入らないオーケストラ作品でしか聴いたことがない人が多いのですが、カラヤンに弟子入りしていた当時の小澤征爾もワーグナーのオペラを振ったことがなかったのです。
Aは突然顔色を変えて、私を論難し始めました。
「それなら、あなたはワーグナーのオペラを全部聴いたのか」と。さらに「オペラなんてくだらない。あんな、ばかばかしい内容のものはない」とも。Aはよほどオペラとオペラを好む私のような人種が気にくわなかったのでしょう。
ワーグナーのオペラを全部聴いたのかと言われれば、全曲のCDを持っていて、通して聴いたのは「トリスタンとイゾルデ」だけで、しかも三、四回しかありません。さらにいうと、「ながら」でしか聴いていないのです。
「『さまよえるオランダ人』を聴いたのか「タンホイザー」や『パルシファル』は」と畳みかけられても、それらも前奏曲に親しんでいるだけで、Aと同レヴェルなのです。
私の口ぶりにもカラヤンの意見に同調するニュアンスが籠められていたのでしょう、彼の怒りが私に向けられても仕方なかったかもしれません。
声楽が入る場合はバッハのミサ曲など純粋音楽は愛好するものの、世俗的なオペラの世界を嫌悪しているAが、ではベートーヴェンの膨大な全作品を聴いたのかといえば、そんなことはあり得ないのでしょう。作品の全部を聴いたかどうかは本来批判の基準にはならないはずですから、逆にやり込める隙間はあったのですが、議論は勢いのある方が勝ちです。
オペラというのは、「通俗」ストーリーのなかで「類型」的な人物たちが、緊急の際にものんびりと歌に託して心情を訴えるという音楽劇です。
「ラ・ボエーム」では、主役のロドルフォが「私は詩人です~」なんて、声を張り上げて自己紹介しても、まともな女性ならさっさとその場を切り上げて帰ってしまうでしょう。
しかし、ローソクの明かりだけで、自分の部屋の鍵を落としたと騒ぐだけの、まことに小さなドラマを、プッチーニはなんと美しいメロディーに載せて聴かせてくれることか。聴き手は、寒い夜の温かいスープ、暑い昼間の冷たい氷いちごに恵まれたときのように、心と体双方の快楽に浸り切ります。オーケストラや楽器のみの演奏では、天に昇る崇高な高揚感は得られても、歌唱がもたらす、譬えようもなく甘い、この快感は得られないのです。
その辺にオペラ好きとオペラ嫌いの別れ道がありそうです。
オペラ好きは、快楽主義者? オペラ嫌いは禁欲主義? しかし、Aは酒好きで、バイクでのツーリング好きです。女性に関しては、黙して語らずですが、肉欲に関しては、抑制的であるように思えます。ひょっとして、肉欲が鍵?
音楽学者・岡田暁生さんの『オペラの運命』(中公新書)のなかの指摘で面白いのは、オペラは禁欲的で市民社会的なプロテスタントとは合わず、享楽的で貴族社会的なカトリック地域で発展したという点です。なるほど、なるほどです。
勝手ながら、音楽に高邁さ、純粋さ、清らかさなど心の浄化を求める層はオペラ嫌い、快感、気持ちよさ、麻薬的興奮など現世の喜びを求める層がオペラ好きということを本稿の小さな結論といたしましょう。