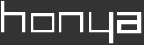ポテトサラダ通信 49
死は「不当な暴力」
校條 剛
大学四年生の時に、フランス語の教育実習をしました。フランス語ですよ! 正式教科として普通の高校では、採用していなかったので、暁星とか早稲田高等学院とかの有名私立高校を選ぶしかありません。大学が早稲田だったので、附属高校である早稲田高等学院が受け入れてくれることになったのは幸いでした。そのとき一緒に教育実習(いわゆる教生)を務めたM君は、高等学院が母校だったので、私よりも学校には馴染みが深かったのです。彼は、大学卒業後、大学院に進み、某女子大のフランス語の先生になったらしいです。彼とは教育実習が終わったあと一度も会うことがなく、音信を知ることもなく、五十年近い歳月が流れ、ついに昨年フェイスブックで巡り会いました。そのフェイスブックのなかで教えられたのが、シモーヌ・ド・ボーヴォワールの『おだやかな死』という著作でした。
ここには、私が長年、心の淵に沈めていた「死」のテーマについてのある明確な姿勢が打ち出されていました。仏教者など聖職者の語る「悟り」への導きなどさらさらなく、「天国でまた会える」というようなおとぎ話的な慰めも示されません。死へと向かう肉体の昼夜を問わない苦痛にうめきながら、それが訪れるまでジタバタし、苦悩する母親と姉(ボーヴォワール)と妹の姿が描き出されています。
「死は誰にとっても不自然なもの」だという認識をボーヴォワールは最後に示します。たとえ、人が老衰や病気で亡くなったとしても、「死は不自然であり、不当な暴力である」と。
本のなかから最後の締めのエッセンスの箇所を引用しましょう。
<「年に不足はない。」老人の悲しみ。彼らの流刑。大部分のものはこの不足のないという年を告げる鐘が鳴ったことを考えない。私もまた自分の母親のことでさえ、この紋切型を利用した。七十歳以上の親なり祖父母なりをなくしたものが心から泣くことができるとは私には理解できなかった。母を失ったという理由で打ちひしがれている五十歳の同性に出逢ったら、私はその人を神経衰弱と決めつけたであろう。我らはすべて死すべきもの。八十と言えば、死人になる十分の資格のある年ではないか……。
そうではなかった。ひとは生まれたから死ぬのでもなく、行き終ったから、年をとったから死ぬのでもない。ひとは何かで死ぬ。母が年から言って死期は遠くないと私が心得ていることが恐ろしい衝撃を緩和しはしなかった。(中略)自然死は存在しない。人間の身におこるいかなることも自然ではない。彼の現存が初めて世界を問題にするのだから。ひとはすべて死すべきもの。しかし、ひとりひとりの人間にとって、その死は事故である。たとえ、彼がそれを知り、それに同意を与えていても、それは不当な暴力である。>(紀伊國屋書店刊。杉捷夫訳)
*この部分をお読みになってお分かりのように、杉氏の訳はぎこちなく、分かりにくいです。ボーヴォワールの専門家による、新訳を求めたいものです。
「不当な暴力」! そう言い切ってしまう作者に脱帽です。というのは、我々は作者の言うように、「もう年齢が年齢だから、死は自然にやってくるよね」などと肉親であっても他人であっても、死を容認するような発言をしているように思います。「諦めきれない」という死ももちろん数え切れないほど起こるでしょう。たとえば、上級国民が犯した池袋の暴走殺傷事故では、誰しも「暴力的な死」に憤ったことでしょう。
ボーヴォワールは、老年になっての死は、生物の当然の運命付けられた自然な帰結だと、母親の死に直面するまでは信じていたようです。しかし、実際に死にゆく母の介護と治療と取り繕った言葉で母の疑惑をそらすといったような欺瞞の十数日(正確ではありませんが)を過ごすうちに、その死生観は劇的に変化します。本来の実存主義者としての思考が目覚めたとでもいうのでしょうか、「死」へのへつらいなど微塵もない激しい抗議の言葉が生まれてくるのです。私にとっても、初めて聞くような抗議の言葉であり、驚かされるというより、「こういう言葉が聞きたかったのだ」という感動がありました。
九十六歳だった私自身の母親の死の間際の様子を思い出します。もう水を口から飲むこともできないほど衰弱していたために、生き延びるには点滴か胃瘻しか方法がないと医者に宣告されたのですが、脳はいたって正常で、「私、死ぬの?」と問われたときに、三人の息子達は誰も返事ができませんでした。その母は、水分を補給されることなく、数日後枯れ木のように干からびて亡くなりました。
この母は、もっと生きたいと思っていたのです。四捨五入すれば、百になる年齢まで生き延びたから、もう死んでもいいなどとは思っていなかったはずです。
おだやかな内容では決してない『おだやかな死』の書かれたのは1964年です。同年の日本の平均寿命は女性72.87歳、男性62.67歳であったので、フランスではもっと数字が小さかったかもしれません。
私は若い頃から「死」というテーマの周りをぐるぐる回ってきたような気がします。私の卒業した大学の文学部では、卒論を書くことが必須で、基本的には一人の作家を選ぶことになります。
私が選んだのはド・ゴール内閣の閣僚でもあったアンドレ・マルローで、テーマは「死について」でした。マルローの小説のなかで一番好きなのは『王道』という作品です。そのラストで、主人公のペルカンは蛮族の住む奥地で自らの死に直面しますが、泣き言を言ったり、懺悔の言葉を吐いたり、聖職者による慰めを求めるようなことはしません。ジタバタせず、それでも熱烈に抗うのです。その人間的な抵抗感が嬉しく頼もしい気がしたものです。
石原慎太郎氏もこの小説の愛読者だったようで、文芸誌「新潮」の編集長だった坂本忠雄氏と次のようなやり取りをしています。
坂本 マルローの「王道」は、好きなんでしょ?
石原 いいね。最後にペルカンが言うじゃない。「死。死などない。ただ俺だけが死んでいくんだ」って。「死」はそれに尽きますよ。
(石原慎太郎、坂本忠雄対談『昔は面白かったな』新潮新書)
若い頃は、私もその部分に惹かれていて、卒論にも引用しましたが、いま『王道』の最後のあたりに目線をさまよわせると、次の箇所に気がつきます。
<永劫の苦痛があってもよい、そのかわり、いかなる神聖な思想も、いかなる将来の償いも、いやどんなものも、人間存在の終焉を正当化しえないのだと、あの犬どものように叫ばせててくれ!>(川村克己訳)
思想的にマルローと常に対立していたボーヴォワールの叫びとあまりに似通っているので驚いてしまうのです。
*第38回<『富士日記』について>で再度、訂正があります。武田花さんの「本名・花子」としたのは間違いでした。本名は「武田花」です。「花子」は百合子さんが発音しやすいから使っていただけだと、埴谷雄高さんが書いています。お詫びして訂正します。