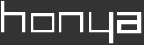ポテトサラダ通信 43
1969年、東大入試中止
校條 剛
『あのころ早稲田で』という本を中野翠さんが書いたときに、いち早く読んだのは、もう二、三年まえになるでしょうか。
期待して読んだのですが、ちょっと肩すかしでした。大学の様相が私の記憶と想像以上に違っていて、のんびりといい青春を送られたようだったからです。彼女は私よりも二、三歳年上で、大学紛争は60年安保時代から絶え間なく続いていたはずですが、私が入学する1969年に向かって煮詰まるまえの時期だったのでしょう。
私が早稲田の第一文学部に入学したのは「70年安保」の前年ということになりますが、実はこの年が翌年の「本番」よりも、大学内の騒乱は激しかったのです。
1969年、この年の1月に東大の安田講堂占拠と排除の騒動が起こり、戦争中を除いて、史上初めて東大の入試が中止されました。現在、この歴史的な出来事を記憶するのは、1969年に大学に入学した同期の連中だけでしょう。歴史的な事実として知っている人たちはある程度いるとしても、それが1969年だったと即答できるのは、やはりこの年に受験生だった我々だけなのです。
私は現役生であった前年、1968年に東大の文科三類(いわゆる文学部)を受験して、一次試験は通過しましたが、二次試験はまったく歯が立たず、気持ちとしては簡単にふるい落とされたという感じでした。
そのときも早稲田には合格していたので、素直に進学する手ももちろんあったのですが、余裕のある経済事情ではなかったので、大学は国公立と両親から言い渡されていました。迷うことなく、一浪することに決めました。
当時は一浪することが極めて当たり前のことだったからという理由もあります。誰もが抱く根拠のない望みとして、一年勉強に励めば受かるだろうという漠とした期待が心の底にあったことも否定できません。
私の将来像は映画監督になることでした。高校卒業の時点でそれは決まっていて、邦画五社の映画監督の皆さんの出身大学がほぼ早稲田、慶応、東大に集中していることを知っていましたから、その三大学のどれかに入ろうという方針でした。しかし、先ほど触れたように親からは国公立を選んでくれと言われていましたので、なんとなく一年勉強すれば、東大に受かるかもという根拠のない理由で浪人してしまったわけです。
高校を卒業後、東大合格者をたくさん輩出している駿台予備校を受験するも落ち、仕方なく高田馬場に教室があった一橋学院という予備校に通い出しました。同級生の顔も何人か見たのですが、だんだんと自宅で一人勉強することでいいのではないかと予備校を辞めてしまいます。その辺の記憶もあいまいになってしまいましたが、予備校に通い続けたという映像が浮かんでこないので、やはり辞めたのだと思います。
頭は映画のことでいっぱい、アートシアターの会員になっていましたので、ときどき上映館の新宿文化に駆けつけたりしていました。伊勢丹のまえのビルの上層階にあった日活名画座でフェデリコ・フェリーニの『8 1/2』を観たのもこの年でしょう。興奮冷めやらず、寝床のなかでも最初のシーンから一つずつ思い出しながらフィードバックしたものです。近所の区立図書館で脚本家 依田義賢さんの『溝口健二の人と芸術』という本を見つけて読みふけったりもしました。
当然、勉強は手に付きません。苦手な理数系はもとより、最初から得意ではなかった古文もほとんど読まず、英語の長文読解も熱が入らず、年号を覚えるのが得意で、唯一自信のあった世界史も東大の二次で中東の古代王朝の出題に音を上げたことで、かえってやる気を失っていました。
若い時代でも日々はあっという間に過ぎていきます。春に浪人生活が始まったのですが、初夏を迎えたころに、まったく受験勉強が進んでいないことに気が付きます。そこで、真夏時には暑い東京を離れて、信州の「学生村」で集中的に勉強をしようと目論みました。静かで涼しい環境に置かれれば、勉強する気持ちになるだろうと、これも多くの怠け者学生が描く他力本願幻想の一つだったわけです。
当時、クーラーが据えられていたのは、個人の家ではまことに少なく、学生達は近所の図書館の勉強室の席を求めて、早朝から図書館前に列をつくったものです。学生村は一種の民宿で、学生の夏休みの学習のためというだけではなく、農家の経済支援の方向で発案されたのでしょう。
私が赴いたのは、小諸の農家でした。農家が副業として、自宅の庭にプレハブのアパートをつくり、学生達は何室かあるその部屋に一人ずつ割り当ててもらい寝起きをするという形でした。
食事は三食付きで、全員で食卓を囲みます。大学生や短大生など、かつてこの家に滞在したことがある二十歳以上の男女も集まってきたので、食卓にビールが載ることもありました。
暑さをしのげるそういう環境に入っても、私は相変わらず、勉強には手が付かず、その農家の長男、次男の小学生達と近くの山野を歩き回ったりしていました。宿泊者のほぼ全員で昼間は野球をやったり、夜は夜で肝試しというので、まっ暗ななかを村はずれの祠まで走ったり戻ったりと、まるごと遊びにきたようなものです。お金を出してくれた親には言い訳が立つ状態ではありませんでした。
しかし、同宿の学生のなかでも、一人は確実に勉強に励んでいました。清水君という埼玉県熊谷あたりから来ていた色白の青年です。
七夕は東京では7月7日ですが、小諸あたりでは、ひと月遅れで行なう慣習でした。8月7日に農家のほうで、笹を用意してくれて、皆で願い事を書き記した短冊を結ぼうということになりました。
私は何を願ったのかまったく思い出せませんが、清水君が「駒場の青春」と記したことを鮮明に覚えています。言うまでもなく、「駒場」は東大の教養学部のあるところです。つまり、来年こそは東大の試験に合格して、東大生になるぞという決意表明でした。清水君の短冊の言葉を誰もからかったりしなかったのは、彼の勉強振りを見ている我々には、彼が合格するのは当たり前ともう常識のように思っていたからです。
東大入試中止が伝わったときに、同じ受験生でありながら、私は自分のことよりも「清水君はどうするのだろう」という心配が胸に浮かんだことを忘れません。
東大入試中止を決定した経緯については、未だによく分からないのですが、東大に入ることを青春時の最大の夢として描いていた受験生たちは、安田講堂事件からも全共闘運動からももっとも遠いところにいた存在であり、社会の憎しみの対象となるには余りに弱い立場の若者たちだったと言えます。
罰するのなら、そのときに東大生になっていた者達のなかから選ぶべきであり、東大に入りたいというけなげな希望を抱いた若者達を犠牲にする権利など国家にも国民にもなかったはずです。
清水君が、あくまでも東大という気持ちを貫いて、もう一年浪人したのか、あるいは京大とか一橋大とかに進路を変更したのか、ひょっとしたら同じ早稲田に入っていたのか、一夏の交流だけだったのでその後を知らないのですが、いまだにふと考え込むときがあります。
当時から現在に到るまで、日頃から、東大という存在を仰ぎ見ながら、同時に憎んでもいる世間の「ざまみろ」という悪意の声ばかり私には聞えていました。
いまさらの話でありますが、安田講堂事件が歴史的なポイントとして登場するときに、その裏には清水君のような犠牲者の存在があったことが語られることがあまりに少ないのは残念です。
「東大に入れなかった言い訳ができて、あなたはよかったのではないか」と問われれば、私は断じてNO!と答えます。人間個々の自由を奪うような社会の制裁には断固として反対なのです。