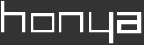ポテトサラダ通信 7
ダダイストと京都
校條 剛
朝日新聞の火曜日夕刊に「京ものがたり」という連載があります。私が京都に仕事を持っていることもあって、いつも読んでいます。少し前ですが、四条大橋の東側袂に近いビルの6階にある「キエフ」というウクライナ料理の店を取り上げていた。加藤登紀子さんのお父さんが開いた店で、お父さん亡きあと、長兄が継いでいます。小さなステージが設えてあり、登紀子さんが華やかな衣装で歌っているシーンが誌面に載りました。
その店も、さっそく知人が来たときに行ってみました。これまで、日本のロシア料理の店で「これは、旨かった」と感心したことは多くありません。神保町にあった「バラライカ」だけが例外で軒並み失望してきたという記憶です。料理の単調さや華やかさの不足、オリジナリティの薄弱さなどで、値段が高い割に料理の性格がはっきりしないということが欠点なのだと思います。「キエフ」でもメインがフィレステーキだったりして、もっとなんとか工夫がないものかと思わざるを得なかったことは事実です。しかし、キノコ入りのつぼ焼きのクリームシチュウは、どこのロシア料理店でも出す料理ですが、クリームソースの旨さが格別でしたし、つぼの口を覆っているパンの味わいも深いものがありました。メインのチキンの料理もちょっとニュアンスに欠けるもののこれまでの料理屋よりも上回っていたと思います。「キエフ」のためにさらにつけ加えますと、窓から障害物なしで、まっすぐ鴨川縁の景色が見通せる点を褒めましょう。なかなか贅沢なロケイションです。
ところで、ここまでは前段なのです。つまり、イタリア料理で言えば、アンティパスト。これからが今回のプリモ・ピアット(第一皿)です。
「京ものがたり」12月16日掲載の分は、「中原中也『ダダ』との出会い」でした。中原中也は、「なかはら・ちゅうや」と読みます。私も最初に知ったときに、「なかはら・なかや」かなと思ったりしたので、念のため書いておいましょう。
中也は、山口市湯田温泉の生まれ、育ち。小学生の頃は神童と言われたのですが、中学に入ると短歌に熱中して、成績が急降下。実家はお金持ちだったので、父親が京都の立命館中学に転入させます。15歳のときだといいます。この年齢で、飲み屋にも出入りするようになります。
四条河原町の高島屋の向い側の路地を入ると、柳小路通りという狭い飲食街があります。といっても、私はまだ足を踏み入れたことがないのですが、このなかの一軒に「静」という居酒屋があり、そこがかつて中也の通った場所だったといいます。時は大正の末期、今から九十年も昔のことである。
中也が通ったのは、「正宗ホール」という名前で、「静」は隣にあったのですが、現在の店主の姑が「正宗ホール」を買い取って一軒の店にしたということです。店の内部には九十年間そのままに残っている部分があるというから驚きます。京都は空襲を受けていないので、多くの寺社は消失を免れて、何百年という時間を背負った歴史的な建物が多いですが、居酒屋のような本来変遷の激しい商売の建物が残っているのは、日本でもこの町くらいでしか考えられないでしょう。その場所に行けば、中也が見た情景をそのまま体験できるということになります。
もっとも、この古い酒場も結構居酒屋ファンの間では有名になっているようです。吉田類がテレビですでに探訪しているということも、「食べログ」の投稿で読みました。「食べログ」では、この店の外観も内部の様子も見ることができます。
さて、京都で中也は、「ダダイスト」と自称し、友人たちからもそう呼ばれていた。中也が短歌から詩に転じるきっかけになったのは、京都に着いて間もない頃に古本屋で購入した『ダダイスト新吉の詩』という一冊でした。この一冊が中也をダダイズムと詩に導いたのです。
やっと、話は本論に入っていきます。これからが、イタリアンでいう「セコンド・ピアット」つまり第二皿。メインの肉料理ですね。
ダダイスト新吉についてお話ししたいと思います。といっても、我が青春時代に新吉の詩に触れて、私も一時かぶれたというようなことではありません。私は、ダダイスト新吉こと、高橋新吉に会っているのです。しかも『雀』という詩集に『湖の女』という小説集と二冊ほどもらってもいます。
高橋新吉は練馬区江古田に住んでいました。西武池袋線の各停に乗って三つ目の駅です。後年、私は日大芸術学部の非常勤講師を務めることになって、この駅にしょっちゅう通うことになるのですが、大学を出て新潮社に入社した1973年に駅前に立ったのが人生最初の機会でした。その後も、およそ縁のある土地とは思っていませんでしたので、土地と人間の結びつきにも運命を感じます。
日芸の講師になってから、新吉の借りていた家を探そうと考えたこともありましたが、駅を降りて左右どちらに行ったのかさえもう霧の彼方でした。多分、左だろうなんて、少し歩いてみましたが、途中でまったく分からなくなり、探索を諦めたこともあります。
新吉が住んでいたのは、しもた屋風の一軒家の二階でした。似たような住宅が並んだうちの一軒だったという記憶があります。当時、私はそこが借家で、ご丁寧にも一階には家主が住んでいるのだと思いこんでいましたが、新吉は結婚もし、子供もいるそうですから、案外一家で住んでいたということだったのかもしれません。
新吉の家になぜ行ったかという事情をお話ししなければいけませんね。単純なことで、詩の原稿を受け取りに行ったのです。先輩の佐々木信雄さんが、詩のコーナーの担当者で、依頼だけは自分でしていましたが、原稿取りはときどき新人にやらせていました。
詩のコーナーが雑誌の誌面にあったなんて、随分文学的ですね。そこが今振り返ると「小説新潮」のいいところだったように思います。
新吉は和服の着流し姿でした。風貌には鋭さが残っていましたが、ダダイストは既に遠い彼方に去ってしまっているのだと外見から明らかに窺えました。あとで調べてみると、1901年生まれの新吉は七〇歳を二つ、三つ超えたあたりだったのですね。禅の思想に深く傾倒していたとのことで、このときにもらった詩集を開くと、仏教的な悟りを思わせる詩篇に出会います。
原稿をもらったあと、故郷から送ってきたという「麦こがし」をご馳走になりました。現在、この食べ物を知っているのは、かなり年代の高い世代でしょう。団塊の世代ですら、この素朴な食べ物を小さい頃に味わったという人がどれくらいいるでしょうか。
私は母親がときどき作っていましたので、よく知っていました。麦こがしは、正式には「はったり粉」というそうです。大麦を焦がして粉上に挽いて、保存食としたものです。食べ方は、茶碗のそこに適量を落とし、水を少し垂らして、スプーンなどで練り込みます。途中、砂糖を加えることが普通ですが、戦争中など砂糖は手に入らなかったでしょうから、素材と水だけで練り物としたのではないでしょうか。それだけでも、ほのかな甘みが舌先に感じられるはずです。
新吉の故郷は四国の愛媛です。当時七〇過ぎだとすると、もう母親は故人になっていたかもしれませんが、私の記憶のなかでは、母親から送られてきたことになっています。
一緒に麦こがしを食べながら、新吉は文学史上有名な戦前の詩誌「歴程」のことに話題を持って行きました。あとで分かるのですが、新潮社の編集者に対して言いたいことがあったのです。
「『歴程』は、草野心平が創刊したと自分で言っているが、違うんだよ」と新吉は言います。「本当は逸見猶吉が作ったんだよ」
新吉は、第一次『歴程』の編集後記のコピーを私に示し、読んでご覧と言います。文面はすっかり忘れてしまいましたが、後記を書いているのは、間違いなく逸見猶吉という人でした。
「新潮日本文学事典では、心平が創刊したことになっている。会社に帰ったら、記述を訂正するように言ってほしい」
私は、これほど明白な証拠があるのに、どうして訂正されないのかが不思議だった。それに、草野心平はどう考えているのかも知りたかった。
「心平の奴はさ、俺がこの問題を持ちだすと、『このキ〇〇イ!』と怒鳴って行ってしまうんだよ」(キ〇〇イ、は放送禁止用語。自己規制しました)
どうやら、長年、新吉と心平のあいだは、この件を巡って険悪になっている様子でした。
私は、文学事典の責任者に必ず伝えると約束して、新吉の家をあとにしました。そして、約束通り、文学事典の担当者に以上の経緯を話し、善処を求めたのです。
結果は、文学事典の記述はそのままでした。どうやら『歴程』についての項目は草野心平自らが執筆したということのようでした。草野は詩壇の重鎮であり、文壇においても高いポジションを得ていましたので、「傍流の」詩人新吉の抗議をまともに受け取ろうとする姿勢は見られませんでした。この問題の検証は後世の学者に任せたいと思いますが、高橋新吉の証言だけでもここで述べておくのがいいと思ったのです。
ところで、中也と新吉ですが、当然会っています。中也は、京都で長谷川泰子という年上の女性と出会い同棲しますが、文学はやはり東京だと考えたのか、泰子と一緒に東京に移ります。中也という人は一種の訪問魔で、会いたいと考えた文人の家を訪れては、次々と交誼を深めていきます。当然、高橋新吉とも知り会いになるのですが、当然のことながら個性の強い二人は衝突します。ある飲み会の席上、中也に対し「暴言を吐き、乱暴を働いた」と新吉は、中也への追悼文で詫びています。乱暴を働いたというのは、ぶん殴ったりしたのでしょうか。中也のからみ酒には皆な泣かされていたそうですから、被害に遭うどころか反対に打ち負かしてしまった新吉はやはり強い人だったのです。
恐いもの見たさですが、中也にも一度会いたかったですね。