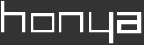ポテトサラダ通信 2
才能と努力
校條 剛
私は、長いこと文藝編集者であった経歴から、十年近くカルチャーセンターで創作の講座を持ったり、小説の作法について本を書いたりしてきましたが、いつも皆さんに述べてきたのは、「才能は自分で開発するもの」ということです。
西村周三氏をホストに据えた「Dr.ジレ!」対談の第二弾は、作家・山本一力氏がゲストです。今回は、山本氏と私のちょっとした因縁についてお話ししたいと思います。才能を自分で伸ばしてきた実例の一人がこの山本一力氏だと思うからです。
山本氏は、私との最初の出会いを忘れているかもしれません。しかし、多分人生の後半に差し掛かって、最初に接触した「文壇」という、一般人には得体の知れない異世界の雰囲気は忘れてはいないでしょう。
私は出版社の新潮社で三つの新人賞の設立に関わりました。関わったという生易しい言い方では相応しくないかもしれません。私が創ったと言ってもいいでしょう。その三つとは、日本推理サスペンス大賞、小説新潮長編新人賞、新潮ミステリー倶楽部賞です。 日本推理サスペンス大賞は、日本テレビの火曜サスペンス劇場のスタッフに私が交渉して設立に持っていった賞金一千万円のミステリー賞です。第一回から第三回まで乃南アサ、宮部みゆき、高村薫という大物女性作家を輩出し、一躍文壇から注目されました。この賞のスポンサーだった日本テレビから撤退を通告され、第七回で終了したために、新潮社独自で新設したのが新潮ミステリー倶楽部賞です。雫井脩介、伊坂幸太郎という逸材を出したものの、たったの五回で終了となりました。
小説新潮長編新人賞は、私が入社以来所属していた小説新潮編集部の長になったときに一般小説の長編部門として作りました。選考委員は井上ひさし、北方謙三、高樹のぶ子、林真理子の四氏で、直木賞や山本賞の選考委員だった井上氏を除いては、まだ選考委員は初めてという残りの三人ですが、北方、林のご両人は後に直木賞、高樹氏は芥川賞という具合に日本を代表する文学賞の選考委員に「出世」したことは、私の選球眼に間違いがなかった証明だと自画自賛しています。しかし、この賞も人気作家を生み出すための「何か」が足りなかったと見えて、結局十年ほどでお役御免となりました。
実はこの小説新潮長編新人賞の第一回の最終候補に山本一力氏がいたのです。山本氏のそのときの候補作は、多分後に、かなり書き直されて祥伝社文庫から発売されています。題名は『大川わたり』。初めて書いた長編小説で、小説新潮長編新人賞に応募して落ちた経緯は山本氏が書いています。
新人文学賞というのは、第一回の受賞者に大物が現われるか、すぐに消えてしまう泡沫受賞者になるか、相反するどちらかの特徴を示すものだというのが、他社の賞も含めて、これまで見聞してきた経験から言えることだと思っています。
日本推理サスペンス大賞第一回の応募作品は押しなべて低調で、賞に選ばれた乃南アサ氏は、最終候補を選ぶ予選委員会で私が強く推したために残ったのですが、正直ミステリー作品としては弱く、大賞ではなく賞金が半分の優秀作に止まりました。
小説新潮長編新人賞の第一回のときも、候補作を編集部で四、五作に絞るのに難渋しました。魅力のある作品が多くて、部員同士の意見が対立したからではなく、残したいと編集者が思う作品が少なかったのです。さきほど述べたように、まったくの低調ぶりでした。
やっと数作を最終候補として残しました。そのなかには鹿児島在住の視力に障害のある高齢者や東京多摩地区の歯科医師の夫人など、人物として見れば興味深い方々だったのですが、いかんせん読者は作家の経歴で本を買ってくれるわけではありません。
この「長編新人賞」は、「推理サスペンス大賞」と同じ方式をとっていて、選考会の当日、開催されているホテルに候補者も呼んでおいて、選考の結果を待ってもらい、そのあとの受賞式にも全員出席してもらうことにしていました。つまり、落ちた候補者も受賞式に臨むことになるのです。受賞式といっても、身内だけのささやかな集まりですが、選考委員は全員揃っています。落選者も直接選考委員から感想と評価、今後の目標の定め方などを聞くという稀有な体験を得られたのです。
前置きが長くなりましたが、私が山本一力氏と顔を合わせて、話をさせてもらったのは、この受賞パーティのときでした。
選考会では『大川わたり』は、かなり手厳しく叩かれました。類型的な人物とストーリー、ドンデン返しも思わず苦笑が漏れてしまうような安手感がありました。選考委員の指摘はいちいち私の考えでもありました。初めてお会いした山本氏は、サラリーマンというよりは、商売を手掛けている町のオジサンという感じで、話し方もその内容もひたすら明るく、その分軽い性格に感じたという印象です。作品から受けていた印象と人物が一致していたと言っていいと思います。このとき、山本氏は四〇代の後半に入っていました。
正直、「この人は運よくこの場所に入り込めたが、これが最後の機会になるのではないか」と確信するものがありました。この作者の力量がこれから飛躍的に高まることなどあり得ないと将来を見越したのです。
ここで、箴言を一つ。「編集者は、予言者ではない」。そう、新人作家が将来どんな大物になるかどうかなんて、編集者には分かりっこないのです。
というのは、一人の新人がロッククライマーのように険しい崖を這い登るように、平地から這い上がって、山の頂点を極めるようになる原動力は、外に現われるものではなく、内部のマグマが為せるものだからです。選考に落ちた新人が、その後、いかにして知恵をつけ、スキルを磨いていくかは、すべて本人の努力に掛かっています。才能という神頼みの言葉よりも、ここにおいては、努力とちょっとした勘の良さが新人を飛躍させる原動力となります。
山本氏は、その後、二年くらいしてでしょうか、「オール讀物」の新人賞をもらったと報告がありました。そして、株式会社文藝春秋から、最初の単行本が出たのです。その小説が『損料屋喜八郎始末控え』です。しかし、送っていただいたこの作品を読もうという気持にはならなかったのです。やはり、『大川わたり』の悪いイメージが頭に残り、「この人は可能性がない」と信じ込んでいたためでしょう。
目を開かれたのは、氏の執筆量が増えて、とうとう『あかね空』で直木賞を受賞したときのことです。受賞する前、候補作になった段階で読んでみて、驚きの声を上げました。冒頭の豆腐を作るシーンを読んだだけで、この作者が出発地点からどれほど先まで足を延ばしていたのかが理解できました。直木賞らしい構えの作品でもありましたので、受賞は当然と思った次第です。
突然、話題は変わります。四十数歳で歌手デビューしたイギリスのスーザン・ボイルのことです。YouTubeで彼女の存在を知らしめたオーディションのシーンを何度も見ましたが、そのたびに感動してしまいます。小説と違って、音楽の圧倒的な優位性は、大勢の観衆の喝采を目の前で受けることが出来る点です。あか抜けない田舎者丸出しのオバサンが「プロの歌手になりたい」と言ったときには、審査員が指摘しているように、観衆もうすら笑いを浮かべていました。しかし、一旦、「レ・ミゼラブル」の有名な歌「夢を見ていたバカな私」(意訳)を歌いだした途端、これほどの意外性に遭遇することがなかったのでしょう、歌声が聞えなくなるほど聴衆の歓声が増していきます。最後は総立ちのスタンディングオベイションです。
歌手でさえ、四十歳を過ぎてもデビュー出来るのです。いわんや、小説家は何歳でもOKなんです。山本一力氏は、やはり四十代のデビューでしたが、六十歳、七十歳を過ぎていても一向に構わない。問題は、山本氏のように、自分を信じ、一直線に目標に向かってにじり寄って行くことが出来るかどうかだと思います。それが、私のこの頃の持論なのです。