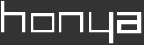ポテトサラダ通信 1
「山田太一氏登場」
校條 剛
この欄を始めるにあたって、自己紹介をいたします。私の姓「校條」は、「めんじょう」と読みます。世の中には変わった苗字が多いことが、最近よく分かるようになりました。テレビ番組で、地方の珍風景とかを訪ねる番組が増え、町や村の普通の人たちが登場することが増えたせいでしょうか。へえー、こんな苗字があるんだ、と感心することが度々ありますね。そういう「珍苗字」の方々も、文字としては読めなくはありません。
たとえば、「樹神」という姓が愛知のほうにあるらしいのですが、これは「こだま」と読むそうです。ですが、「樹」は「木」に通じていますので、「こ」と読むことは可能ですし、「神」は「霊」とは隣接しているので、こちらも「たま」と説明されれば、読めるのです。
私の苗字の上の字の「校」は、日本どころか中国、韓国の隅々まで経めぐっても「めん」とは読めません。自慢になることではありませんが、完全な当て字といっていいと思います。もっとも、この苗字の源泉は「毛受」と考えられます。この姓は「めんじょう」「めんじゅ」などと読みますが、「毛」は「綿」と同じ繊維として兄弟ですから、「もう」→「めん」と変化したものと思われます。「受」のほうは、そもそも「じゅ」と発音していたのでしょう。「じゅ」→「じょう」も無理な変化ではないように思いますが、いかがでしょう。
毛受で有名なのは、かの賤ヶ岳の戦いで、敗走する柴田勝家の身代わりとなって討死し、秀吉にその忠君を讃えられ、塚まで設けてもらった毛受勝助です。ですから、私は柴田勝家の家臣の子孫を自称しています。
次に、このコーナーのタイトルが、なぜ「ポテトサラダ通信」なのかを説明します。長い会社奴隷から解放された三年まえに、個人事業主になり、青色申告をする身となったときに、税務署に届け出た個人事業主としての「屋号」が「ポテトサラダファーム」なのです。「ファーム」は、「農場」ととっていただいてもいいのですが、私のつもりは「FIRM」のほう、つまり「会社」という単語のほうにあります。
そもそも私の大好物の一つがポテトサラダですから、それを「社名」として選んだのですが、最近のポテトサラダの人気の凋落には嘆かわしいものがあります。銀座7丁目のライオンビアホールは、私のお気に入りの店ですが、二、三年まえに、生ビール大ジョッキとともにこの一品を注文した時に、「メニューから外しました」と言われショックでした。つい最近も新宿小田急ハルク地下の老舗ビアホール「ミュンヘン」でも同じ仕打ちに遭わされたのです。さらに、レジの男性からは追い討ちをかけられるように「要するに売れないからメニューから外したんです」と冷酷なコメントを聞かされました。
神保町の「ランチョン」は、東京最後の砦として、ポテトサラダの伝統を維持してほしいというのが、今の私の願いです。
というわけで、私のブログのタイトルは、こうなったというわけです。
前置きが長くなりました。「ドクター・ジレ」の第一回のゲストは、私とは三十年のお付き合いになる山田太一氏です。
その昔、小説雑誌「小説新潮」の一編集部員だった私も編集長も、自分たちの雑誌だけに書いてくれる作家が欲しいね、と常々話し合っていました。方法の一つは、自分たちの雑誌の新人賞を受賞した新人作家を登用することですが、どんなに作品の内容が面白くても、読者の目は名前の売れた人気作家に向いてしまいます。新人ばかりの目次をつくろうものなら、その月の売れ行きはかなり悲惨な数字をはじき出すことでしょう。
自分たちの雑誌だけのオリジナルな色を出しながら、しかも、ビッグネームである作者を探してくるというのが、当時の命題でした。各誌とも考えは同じで、作詞家やコピーラーター、俳優などに小説を書いてもらうことが流行っていたのです。
私は映画とテレビの脚本家に照準を定めていましたが、常に念頭にあった名前は山田太一氏でした。同じ山田でも、山田洋次氏のことはまったく興味が湧かなかったのは、単に、私が「寅さん」シリーズを気に入っていなかったせいです。それは、ともかく、山田太一さんのどこに惹かれたのかというと、「この人は小説を書ける」という直感を得たからでした。
山田さんはすでに小説を発表していました。現在でも話題に登ることの多い『岸辺のアルバム』は実はテレビよりも東京新聞での小説連載が先でした。ほかに中央公論社でも小説を刊行していて、まったくの素人ではありませんでした。生意気ですが、私の目にはまだ脚本家が余技で書いた小説の域を出ていないと感じられたのです。
この山田さんに本気で小説を書いてもらおうと思ったのは、氏のテレビ作品をいくつか見てからです。山田さんのドラマは、どれも最初の第一回で、「危うさ」を感じさせます。「これは、無理だなー。途中で破たんしてしまうのではないか」という強い危惧を感じさせるような設定なのです。たとえば、その当時は偽物臭かったガードマンに英雄的なロールを割り当てるとか、男女の同級生同士に友情を成り立たせるとか、互いに反発している老人と若者に気持ちを通い合わせるとか、今日に至るまで山田ドラマが提出してきたものは、「無理な設定」から発していて、本来なら続くはずのないストーリーを綱渡りのように展開させ、視聴者をハラハラさせずにはおきません。
山田さんは強引に通常の展開を捻じ曲げていきます。剛腕のピッチャーが大打者を打ち取るように、視聴者が「無理だよ、無理」とあきれているうちに、ドラマに幾つも山を仕掛け、視聴者を巻き込んでその障害を越えさせてしまうのです。あとに残るのは、「やった!」というカタルシスです。
山田さんの華奢な外見にどうしてこんな巨大な力があるのかと思うような、ボルテージの高いドラマ展開を体験しながら、「この人は小説が書ける!」と確信したのです。
山田さんに小説の依頼をしてから、三年ほど時間が必要だったでしょうか、初めて書いていただいたのが『飛ぶ夢はしばらく見ない』(1985年単行本刊行)です。次には『異人たちとの夏』の原稿をいただき、その次は『遠くの声を捜して』でした。この三作は、山田さんがファンタジー三部作と自ら名付けられて、氏自身の仕事のなかでも特別エポックメイキングな作品群とされています。
最近の山田ドラマは、一貫して老人問題を扱っているように思えます。つい最近の単発ドラマ「よその唄 わたしの歌」でも、高年齢者の「ひとりカラオケ」を題材にして、山田さんにしかできない流儀でドラマ展開されています。
西村周三氏をホストに始まる「ドクター・ジレ!」対談の第一回として、この方を措いて、他には考えられないと私は考えました。タイトル「ぼーっとしてたっていいじゃないか」は、まさに山田式反語的な言い方です。