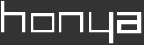ポテトサラダ通信 67
泣き虫弱虫酒見賢一逝く
校條剛
昨年(2023年)は多くの作家の死が伝えられました。前半では平岩弓枝さん、森村誠一さんで、このシリーズブログでは平岩さんについては、すでに書いています。しかし、秋以降がそれこそラッシュのように、私が編集者として交流のあった作家と編集者の方々の訃報が報じられたのでした。これはかなりのショックでした。自らがそういう巡り合わせの年齢になっているのだということではもちろんあるのですが、それにしても皆さん死に急いでいるようで心が痛みます。
その作家の方々の名前を挙げると、酒見賢一氏、伊集院静氏、山田太一氏、西木正明氏の四氏になります。編集者では先輩のお二人、新潮社の岩波剛氏、文春の中井勝氏(ペンネーム森史朗)。どなたを選んでも思い出がありますが、今回は文壇交際の狭さから追悼の記事が少なかった酒見さんのことをお話ししようと思います。
タイトルの「泣き虫弱虫」というのは、本人がそういうタイプの人間だったと私が決めつけているわけではなく、2004年に彼が発表した小説『泣き虫弱虫諸葛孔明』からもらったものです。しかし、だんだんと彼は自分のことを言ったのだとも思えてきました。
笑わない男でした。唯一人前で笑ったのは、1989年の第一回日本ファンタジーノベル大賞の受賞時に、讀賣新聞の全面広告で彼の顔が大写しで紙面を飾ったときでしょうか。もちろん、笑うというより微笑んでいるのですが、何度か会ったときにも、このような穏やかな微笑みを浮かべていたことは記憶にありません。2000年に新田次郎賞を受賞したときに二次会を銀座のバーで催したときにも、とうとう笑い顔がなかったと記憶します。
酒見さんは多分、芯から幸福感を感じることがない人だったのではないでしょうか。ガンマニアでもあり、彼のマンションの自室にはそういった趣味の品物で溢れていましたので、そういう一品を手に入れたときには、嬉しそうな表情になったのでしょうか。少なくとも我々編集者に見せた顔は常に口を尖がらせた不機嫌そうな顔でした。文壇に対してだけではなく、社会のすべてに不満があり、その不満を解消するのは小説のなかだけでだったのでしょう。
長大な小説『陋巷に在り』を「小説新潮」で連載していたとき、私は編集長であり、神楽坂の居酒屋、豊橋の居酒屋やカラオケ店で何度か酒席を一緒にしましたが、編集者についても彼なりの理想像があって、いわゆる無頼型の編集者に理想像を見出しているようでした。サラリーマン編集者が好きではなく、おそらく昔の編集者に関する本を読んでいたのでしょう、我々にも無頼な行動を求めたいようでした。私は無頼派ではありませんが、一種の酒乱(?)ですので、多少彼の理想とする編集者に近かったのでしょうか。
酒見賢一氏が亡くなったのは2023年11月7日。新聞の訃報欄には「呼吸不全」によるものとありました。この用語は死亡時の状態を表わしていますが、病因を示しているわけではありません。では、彼を死に至らしめた病気があったのかというと、それはおそらく彼しか知らないことなのでしょう。
長年、出身校の愛知大学豊橋キャンパスの近くに単身暮していた彼が、故郷の久留米に戻ったのは、亡くなる一年ほど前だったということです。それから亡くなるまでの事情は実家を守ってきた弟夫婦にしか分かりません。弟さんのところに連絡を入れた新潮社のT氏によれば、体調がすぐれないので、ちょっと入院すればよくなるだろうというくらいの軽い気持ちで病院に入ったそうです。しかし、その夜から病状が急変し、翌朝に息を引き取ったとのこと。デビュー年齢が早かったので、まだ還暦も迎える前、五十九歳でした。
私は新潮社を2010年に退職後、2014年春より大学の教員になりました。京都造形芸術大学(現在は「瓜生山学園・京都芸術大学」)の文芸表現学科の学科長として赴任したのです。最初の年は、東京から毎週通っていましたが、翌2015年の2月から単身京都で住むことになりました。それもあって、京都の私の部屋に泊れるようになるので、遊びにお出でになりませんかというお誘いのメールを送ったことがあります。
——————-
前略
校條さんが、大学の先生になられたと聞いて、ビックリしておりました。何があったん
だろうかと。単身赴任ですか。
校條さんがいるのなら、京都旅行に出掛けるのも悪くはありませんね。
わたしの最近の状態は、小説を書いてはおりますが、自分で作家と名乗るにはまだ遠い
状態です。ですから、他の作家さんの批評、悪口などは一切しないようにしております。
とにかく、書かねば作家と呼べません。しかし水道の水がチョロチョロ出る位しか、言
霊が来ないので、新作に乗り出せないでおります。年に二冊はだしたいものです。
それではまた機会があれば。
校條様
酒見賢一拝
——————-
この返信メールをもらったのは、2014年の10月半ば過ぎでした。私はまだ東京から毎週京都に通っていましたが、大学が左京区高野に所有するマンションの一室を借りるつもりになっていました。そのマンションは一家族が暮らせる広さがあるというので、酒見さんが来れば泊まれるからという意味のお誘いをしたわけです。
『後宮小説』でデビューした酒見さんの溢れるような才能のきらめきを長年見てきた私には、「チョロチョロしか水が出ない」という状態の報告には驚きましたが、自己評価の低い彼のことですから、またいつもの癖が出ているなくらいに思っていました。
しかし、その後の作品数の少なさというかほとんど休止状態の彼を見るにつけ、このメールの言葉が蘇ってくるのです。生涯独身で妻はなし、東京の編集者などと話す機会もないような状態でひたすら自室に籠っているだけだったのです。鬱に近い精神状態だった可能性も否定できません。
しかし、それ以降、彼からのメールが届くことはなく、私もハードな教務に追いやられていったため、再度の誘いを掛ける余裕がありませんでした。大学が用意しているという団地の部屋を視察にいきましたが、老朽化の極のまさに陋屋でしたから、自費(大学は負担せず!)で直すと、百万円はかかってしまうという代物でした。この大学の非常識さに呆れて、市の中心のワンルームを借りました。当然、そこには酒見さんを呼び寄せるようなスペースはありませんでした。
そして、上記のメールから十年、酒見さんは、両親は没していたものの、唯一の家族の元で死に場所を得たわけです。
久留米出身の酒見さんがどうして、1989年の作家デビュー後に東京に出てこないで、また故郷に戻ることもなく豊橋に居続けたのかというと、彼の説明では愛知大学の図書館に執筆に必要な資料が沢山あるからだということでした。たしかに、愛知大学は『中日大辞典』を完成させた、中国と縁の深い大学ですし、国内ではここだけという貴重な資料が保管されているようです。
酒見さんは常に「人の理想」の追求者であったように思います。その考えは『陋巷に在り』の顔回の言動によく表れています。しかも、作者にはまだまだ孔子と顔回の本質に届いていないという気持ちがあったのだと思います。人間の本質は一か所に留まるものではなく、水のように流れ、形をなさないものだという認識が酒見さんにはあったのでしょうが、それでも本質をなんとか掴もうとした苦闘のあとが『陋巷に在り』には随所に見られます。それは、『翔ぶが如く』で司馬遼太郎氏が西郷隆盛の人物像を摑まえることに四苦八苦し、周辺から攻めていくような方法を選んだ姿に似ているように思えます。酒見さんは司馬文学を尊敬していました。
といっても、さすが『後宮小説』の作者だけあって、堅苦しく、「お勉強」的な内容だと思わないでください。古代の儒者は霊能者であり、サイキック的なエピソードでは、物凄い躍動感が感じられます。
この『陋巷に在り』の連載はあまりに長期にわたって、終わりが見えないことに編集長の私が危惧したため、ある節目で一旦停止してもらいました。その意味では、酒見さんの作家としての勢いを削いでしまった責任の一端は私にあったのだと思っています。この作品は新潮文庫ではすでに紙の本は廃版になっていますが、電子では購入可能です。Amazonの読者レビューにあるように、読みだしたら止められなくなり、いつまでも中国古代世界に浸っていたくなること間違いはありません。
酒見死すとも、小説は残る。