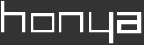ポテトサラダ通信 52
安岡章太郎のエッセイ
校條 剛
村上春樹さん原作の映画『ドライブ・マイ・カー』が話題になっています。映画は未見ですが、内容紹介などを読んでいると、どうやら登場人物が舞台俳優でアントン・チェーホフの「ワーニャおじさん」に出演するため、セリフを覚えようとするらしいです。この戯曲は学生の頃一度だけ読んだことがありますが、もうすっかり忘却の彼方です。映画を観る前に、もう一度、読んでみようと思いたちました。
チェーホフは私の若い頃もっとも愛読した作家の一人ですし、中央公論社版の『チェーホフ全集』は蔵書中、もっとも大事にしている書籍です。戯曲が集められた第十二巻を取りだしてきて、黒と赤だけの今見ても美しいデザイン箱から中身を取り出します。表紙を開くと、はらりと月報が落ちました。二人の作家がチェーホフにまつわる思い出を書いています。大岡昇平と安岡章太郎です。大岡は大好きな作家ですが、今回のエッセイを続けて読んでみると、安岡のねそべったような姿勢がエッセイというものの骨法を示しているように思えて、感心してしまいました。そのエッセイは「ヤルタのチェーホフの家」と内容そのままのタイトルが付けられています。
黒海の沿岸にヤルタという避暑地があり、チェーホフの短篇「犬を連れた奥さん」で知られた町ですが、そこにチェーホフは別荘を持っていました。その別荘への訪問記なのですが、最初から安岡はやる気を見せません。なにしろ、ここはロシアの誇る作家の一人チェーホフの家ですから、国内外からの観光客や学生たちで内部も周囲も取り囲まれているのです。
安岡はもう見なくてもいいという気持ちになっています。しかし、どうしても見せたいのが現地の案内人です。そして、夕方になり当たりは暗さを増し、見物客が減ってきたので、思いのほか早く家のなかに彼らは入れます。
エッセイというものは、このように書くのだという見本を見せられたように思いました。つまり「やる気を見せない」ということ。動物に譬えると、犬よりも猫の姿勢ということになるでしょうか。
しかし、このやる気のない作家が優れているのは、「見るべきモノは見ている」というところではないでしょうか。部屋の中はもう暗くて、窓際のものが仄白く見えるだけだと作家は書いています。しかし、書斎の椅子の後ろに壁にかかっていた絵のことだけは覚えていると言うのです。
それは、横長の新聞紙大の水彩画で、草原の中を小川が流れているというだけの風景画でした。
<しかし、その草原の柔らかな緑は、たしかにチェーホフが何にひかれていたかを簡明に語っており、チェーホフがなぜこの国の人に愛されているかということも、その風景画の不思議な明るさを見るとわかる気がした。>と。
この絵はおそらく、チェーホフの友人でもあったレヴィタンの絵だったでしょう。安岡章太郎は薄暗い部屋のなかで、その風景画だけに目が吸い寄せられていく筆致で描いています。エッセイはこのように「発見と感動」を締めに持ってくると、読み手の感動はいやましに高まるのです。
以上は、ロシアがウクライナを侵略するまえに書き始めた題材です。この時点で一言付け加えると、プーチンはチェーホフなど読んだことがないか、一つは読んだことがあるが自分には何の関係もない世界だと本を放り投げてしまったかのどちらかだと思います。