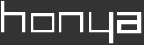ポテトサラダ通信 37
ゆく夏の無言館
校條 剛
本年2020年8月9日の日曜日のNHK・Eテレ「日曜美術館」は、信州上田市にある「無言館」を取り上げていた。
この美術館は、熱暑の夏に訪れるのが一番相応しい。特に原爆が落とされ、終戦を迎えた8月、とくに下旬に訪れるのがベストである。夏は死者が戻ってくる季節であり、また夏の終わりは死者が去っていく気配が濃厚に感じられる時期であるからだ。
照りつける太陽光を逃れて、この美術館に一歩足を踏み入れると、分厚いコンクリートの壁に守られた内部は、人工のものではない自然の涼しさに満たされていて、たちまち汗が引いてくる。そこに飾られている若々しい絵画の作者は、75年まえに終わった戦争で命を失った上野の画学生達である。現役生もいれば、十年以上以前に卒業して、各地に散らばっていた人たちもいる。
その絵画はいまも新しい息吹を伝えているが、作者の皆さんがすべて戦争で無駄死した方々と知っているので、自然訪れた我々は絵のまえに無言で立つのである。これが「無言館」である所以なのだろうとまずは気がつく。
私がこの美術館を最初に訪れたのは、開館して間もない1997年だろうと思う。無言館の館主は美術蒐集家の窪島誠一郎氏であり、その実父は作家の水上勉氏であった。当時、上田市からすぐの小諸市の山地に暮らしていた水上氏を訪ねて、小説雑誌編集者であった私は東京からやってきていた。原稿の打ち合わせをするためか、新築なった小諸の家を見るためかすっかり忘れてしまったが、氏のもとを辞去する際に「窪島が美術館を作ったから見ていってやってくれよ」と言われたのだと、そこは覚えている。
タクシーを呼んで、「無言館」までひとっ走りしてもらった。どういう内容の美術館か説明を受けていなかったので、入館してから戦没画学生の絵を展示していることを知った。作者は、戦地で無念の死を遂げ、そのときから言葉を持たない無言者に変わった。絵のまえで、ここを訪れた我々が無言になるのと、画学生達が無言であることのダブルミーニングであることに気がつくのはこの瞬間だ。
浴衣を着た妹を描いた号数の大きな絵、家族や妻や子どもを描いた絵、もちろん風景画、若々しい感性に満ちあふれた作品が並ぶ。その作者のプロフィールと学生時代の写真なども加えて、行き届いた解説を読むうちに涙が目尻ににじんできた。芸大祭のときの仮装大会、レンブラントの扮装で会場を賑わせたであろう男性は、銃撃され、中国の農村の泥濘にまみれて死んだのだろうか、あるいは太平洋の暑熱の小島で飢え死にしたのだろうか。レンブラントに傾倒し、ベートーベンのSPレコードに熱狂していた画学生の二十年は本当に無駄に消えてしまったのだ。
私が政治家の靖国神社参拝を聞くたびに不愉快になるのは、こうした一人一人の戦死者への哀惜がまったく無視されているからだ。他国を意識した「日本」という抽象的な概念にこだわるよりも、一人の日本人の死を惜しむ想像力がほしいと願いたいが、政治家というがさつな人種には無理な注文なのだろう。
無言館の絵は、窪島誠一郎氏が展示されている画家達の同窓生でやはり戦争に駆り出され、シベリア抑留まで体験した野見山暁治氏の協力を得て、戦没画学生達の実家を回って集めたものだ。その野見山氏が2020年8月現在、99歳で存命なのは嬉しいことである。
ちなみに、野見山氏とは面識がないが、まったく縁のない人物というわけではない。義弟の作家田中小実昌さんとは長く担当編集者としてお付き合いしてきたのだし、コミさんの奥さんは野見山さんの妹のマドさんだ。練馬区氷川台に家を建てた野見山さんが、隣の土地が空いているよと義弟夫婦を呼び寄せ、私が新築成った超モダンな家を見学に訪れたときが昨日のことのようだ。後に、コミさんはロサンゼルスで客死し、奥さんもその数年後に亡くなり、さらに次女のりえさんまでガンのため早世してしまった。
その後、無言館を再訪したのはいつのことだったろう。もう十年かそれ以上まえのことになるだろう。このときは妻にも見せたいという理由があったのだが、それ以上に一度では物足りず、また暫くすると再訪したくなる気持ちの乾きを覚えるというのが最大の理由だったと思う。再訪の夜は、上田駅の近くのホテルに泊まったはずだが、どのホテルに泊まったかということの以前に、泊まったことさえ忘れている。無言館の印象がほかの瑣末事を圧してしまっているのだ。
最初に書いた「日曜美術館」の放送のなかで、一番感動した場面を述べなくてはならないだろう。無言館の入り口には、来館者が一言感想や思いを記すためのノートが置かれている。そのノートに、終戦からほぼ50年後、おそらく開館間もない1997年頃に一人の女性が長文をしたためていたという。館長の窪島さんが、その文章を読み上げる。この番組中のハイライトシーンだ。
その一文は「私、来ました」と始まる。そして、展示されている一枚の裸婦像のモデルが自分であることを告白し、いまは亡き美大生に語りかけるように文を綴っていく。彼女は東京・下北沢に住んでいた美大生の画家のもとに何度か通い、アパートの部屋で裸になって絵のモデルを務めたのである。素人ゆえに、最初から最後まで恥ずかしさを拭えずに、消え入るような面持ちでいたところ、美大生が優しく抱き留めてくれたこと。美大生が戦地で亡くなったあと、戦後は生きるために必死で気がついたら独身のまま50年経ってしまった、と。
モデルになったときに20歳だとしたら、無言館を訪れ、かつて下北沢で描かれた自分の姿に接したときには、70歳になっていたろう。それから、25年が過ぎている。存命だとしたら(十分可能性はあるが)、95歳である。この女性は25年前の再会からあと、何度かまたこの絵のまえに立っただろうか。そんなことも気になってしまった。
この夏、三度目の再訪を予定していたが、おそらくそれは無理だろう。新型コロナの猛威が移動の自由を奪ってしまったからだ。身体的には移動できても、気持ちの自由が失われてしまっている。来年の夏は是非、いやどうしても訪れるつもりでいる。