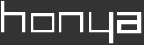ポテトサラダ通信 28
ダンスの時間
校條 剛
最近、ダンスというものについて考えることがあった。ダンスといっても、社交ダンスというか、外国のナイトクラブとかダンスホールとかで踊る、男女が組になるダンスのことである。かなり昔だが、妻からダンスを一緒に習いに行こうと提案されたことがあった。運動量も多く、一通りの練習メニューを終えると汗だくになり、健康のためにもいいというのが補足の理由だった。もちろん、ダンスをすること自体の楽しさが第一の理由であったことは言うまでもない。そのときは、一笑に付していたのだが、逆に今こちらから誘っても、妻のほうがその気が失せてしまったようだ。
多分、あり得ないが例えば豪華客船で日本一周くらいの軽いクルーズに参加したとすると、客船内では毎晩ダンスパーティが開かれるだろうし、勘のいい妻はともかく、不器用な私はステップを覚えるのにも四苦八苦するに違いない。
「飛鳥」などの豪華客船に何度も乗っていた作家の内田康夫夫妻やイラストレーターの長尾みのる夫妻などは、ダンスはセミプロ並みだったはずだ。とくに奥さん勢はことのほかダンスに熱心だったので、二十年近くまえだろうか、内田夫妻の主催で東京恵比寿のウェスティンホテルで、編集者を集めたダンスパーティが催されたこともまだ記憶に新しい。内田さんが亡くなってしまっているくらいだから、随分昔のイヴェントなのだろうが、最近そのときのスナップが何枚も出てきて、当時は太っていた自分がホテルで借りたタキシードをまとって、集英社の女性編集者にリードされて(?)、一応踊っているのが笑えた。このときウェスティンのタキシード借り賃は、四万円以上だったが、後輩の上田君はデパートから二万円で借りたと聞いて、公費だったとはいえ判断ミスを大いに嘆いたものだった。
確か長尾さんの奥さんはコンテストの最終に残るほどの腕前だったはずで、長尾さんには「船上ダンスの勧め」という感じのエッセイを書いてもらったこともある。その長尾さんももう鬼籍に入ってしまっているのだから、座業の男性陣はたまのダンスくらいでは寿命が延びないのか。
今日、いきなりダンスの話を持ってきたのは、これまで実感として理解していなかった、ダンスというものの身体感覚と精神面への影響に思いをはせる機会があったからである。それは、一年くらいまえの京都一人暮らしのさ中、シャンソンの「小さな三つの音符」をコラ・ボケールの歌で聴こうと、YouTubeを開いたときに、当然なのだがフランス映画「かくも長き不在」(原題も同じくUne aussi longue absence)の有名なダンスシーンがそこだけ選ばれてアップされていたのだ。最初にこの映画を観たときから感動を禁じえなかったシーンであったが、あらためて見入っているときに、ダンスというものの奥の深さが痛いほど伝わってきたのだ。ダンスというのは、単にダンスすることではないという気づき。つまり、単なる運動とか娯楽とかではないということに思い当たったのだ。
男女が身体を接して、手と手を結び、女性は男性の肩に片手を置き、男性は女性の胴に片手を回す。男女とも、異性の身体が生き物独特の柔軟性と、生き物特有の体温を持っていることに初めて気づく。男性の身体は固くしまっていて、女性の身体はなんと柔らかいことだろう! 特別なことを話すわけではないのに、耳元で囁かれる言葉が快く音楽のリズムと同期する。ほかのカップルとぶつからないように、合体した二つの身体は、輪を描き、前後に、左右にと動くのだ。二人には肉体的に外側だけのわずかな接触なのに、気持ちが一つに合わさるような時間が流れる。肉体を超えた、精神の合致、それがダンスというものなのではなかろうか。
「かくも長き不在」では、踊るカップルは一組だけ。パリの外れだか、地方都市なのかは分からないが、町のカフェを女一人で切りまわしている女性(アリダ・ヴァリ最高の演技!)と川のほとりで野宿している捕虜収容所帰りの浮浪者のカップルは客のいない夜に静かにダンスをする。ダンスの伴奏曲は「小さな三つの音符」。音楽の高まりに従って、その浮浪者が行方不明の夫ではないかという確信がだんだんと強くなって、彼女は男の後頭部の戦争中に受けたらしき、細長い傷跡に指を這わせるのである。
この映画が、マルグリット・デュラスの脚本であることを今回初めて知った。デュラスは、私の贔屓の作家の一人である。若いころもっともっとデュラスを読んでおきたかったなという後悔もあるのだが、やはりこの映画は脚本と演出のよさに乗って、演技陣が素晴らしい。そして、このダンスシーンはこの映画の頂点を形作っている。私もやっとダンスというものの本質に目覚めたのである。まだダンスをしたこともないのに「本質」などとは偉そうなので、別の言い方をすると、なぜ、男女はダンスをしたがるかが少し分かったというべきだろうか。
ダンスのシーンで有名な映画は、もちろん沢山ある。「風と共に去りぬ」では、レット・バトラー役のクラーク・ゲイブルと未亡人の証の喪服でダンスするヴィヴィアン・リー。彼女はセンチメンタル映画の極致「哀愁」のなかでは「蛍の光」に乗って踊っていた記憶がある。ヴィスコンティ監督の「山猫」は私観では傑作ではないが、カルディナーレが初登場するダンスシーンは素晴らしい。カルディナーレがスクリーンの枠のなかに現れたときに、画面が膨張したように大きくなり、ボルテージの高まるのを感じた。
メジャーな映画ではないがダニエル・ダリューとヴィットリオ・デ・シーカ主演の「たそがれの女ごころ」(なんと嫌な邦題だろうか。原題はMadame de …。「某夫人」)では、この二人のカップルが夜を徹して踊り続ける。それも一夜のことだけではなく、何夜も何夜も続くのだ。音楽はジュルジュ・ヴァン・パリス。監督は、移動撮影大好き人間マックス・オフュールス、高貴なセンチメンタリズム映画を得意としていた。このダンスシーンだけでも、この映画を観る価値がある。ここでも、ダンスは単なる恋愛遊戯の道具としては描かれていない。男女二人の精神のつながりとして迫ってくるのである。いつ果てるとも知れぬダンスに興じる二人は妻あり、夫あり。結婚したい、法的に結びつきたいという思いではなく、お互いの強い恋情を永遠に感じていられるのが、ダンスの時間なのである。音楽を奏でる楽団員は、眠たくて欠伸を連発しているが、心が合体している二人はお構いなし。この映画は救いようもない結末を用意しているのだが、それだけに一層、このダンスシーンの麻薬的な快楽が後々まで残るのである。後を引く映画だ。
周防正行監督の「Shall we ダンス」を観ていないのは、大失態ではあるが、今日のところはこの程度の話で収めることにしよう。