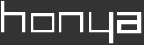ポテトサラダ通信 3
テニスボーイだったころ
校條 剛
2014年テニス・グランドスラムの初頭を飾るオーストラリアン・オープンが1月にあった。女性は中国人、男性はスイス人が優勝という結果。私は、前年のウィンブルドン以来、サビーネ・リシキーのファンになっていたので、彼女の動静を注目していたのだが、まったく名前を聞かなかった。どうしたのだろうと思っていたのだが、全豪の試合は有料のWOWWOWでしか放送しておらず、入会していない私には情報が足りなかった。
私は、男性の試合は見ない。20年くらいまえからだろうか、弾丸サーブを連発するビッグサバ―しか勝てなくなっていて、長いラリーの末にやっとワンポイントものにするといった、しぶとい試合が見られなくなったからだ。女性のサーブも随分と早くなっていて、200キロ近いスピードの持ち主もいるが、やはり女性の試合の特徴はラリー戦であるから、ラリーこそテニスと思っている私にはしっくりくるのである。しかも、男の選手は汗まみれで汚ならしく感じることが多く、比べて女性はきれい好きだから、食事をとりながら観ることもできる。
昔、もう30年くらいまえの男子テニスは、今よりもずっと面白かった。ジミー・コナーズ、ビヨン・ボルグ、ジョン・マッケンローというビッグスター三人の時代で、彼らが今の選手よりも強かったのかどうかは分からないが、少なくともプレイのスタイルと人間的な魅力は、没個性的な現在の選手たちとは段違いに個性的で、極端と言えるほど独特だった。あらゆるスポーツにおいて、超一流の選手はプレイスタイルが普通の選手と著しく異なっている。野球の長島や王、落合などの打撃スタイルを思い出してもらえば、誰にも納得ができる理屈だと思う。無個性化は、時代のせいもあるのだろうか。不思議なもので、テニスのようなスポーツにも時代性は反映するものなのかもしれない。
私がテニスの試合を観だしたのは、自分がテニスを始めていたからである。大学生のときだと思うが、初めてラケットを買った。KAWASAKI/DONNAYと大きな文字で書かれた木製のラケットだった。真っ白の下塗りのうえに赤文字で、そのラケット名が書かれていたのを気に入ったのだ。このラケットは、スイートスポットに球が当たると「ボイーン」と抜けるような素晴らしい音がしたものだ。これほどいい音を出すラケットには、その後一度もめぐり逢わなかった。このメーカーのラケットは後にトップスピンの王者ボルグの公式ラケットになった。ベルギーの会社だが最近とんと名前を聞かない。どうしたのだろうか。
私がテニスに興味を持ったのは、一つは加藤周一の『羊の歌』の影響がある。この本のなかで加藤は、大学生のときの夏休み、軽井沢のテニスコートで白球を毎日追って過ごした日々の回想をする。文学、テニス、輝かしい夏の日々という組み合わせがなんとも快く私の五感を刺激した。秋になり、大学の先生たちも東京に帰ってしまった高原に妹と残った加藤は、ボードレールの詩の一節を口ずさむ。
さらばよさらば つかの間の夏の光の激しさよ!
もう一つ、背中を押してくれたのは、テレビで偶然に観た「10万ドル・マッチ」という触れ込みの当時のチャンピオン、オーストラリア人のジョン・ニューカムと若き挑戦者ジミー・コナーズの一戦だった。コナーズは、ウィルソンのメタルフレームのラケットを全力で振り回していた。バックハンドは初めて目にする両手打ちだ。フォアは誰でもある程度の強打が可能だが、非力なバックはスライスという打法に頼るのが普通で、フラットに打っても、そう何度も強打していられないだろう。コナーズは、なにしろ両手で野球のバットのように振り回すのだから、打球は弾丸のように相手コートに叩きつけられる。
「凄い! 凄い!」と興奮するしかなかった。テニスって、こんなに物凄いものだったのかと、すっかりコナーズの気迫が乗り移ってしまった。
だが、本格的にテニスに取り組むことができたのは、学生を卒業し、会社に入って数年後、28歳のときに結婚してからである。新婚生活を過ごすことになった世田谷区北烏山の近くに会員制のテニスクラブがあって、そこにエイヤッと入会したのだ。キタノアートテニスクラブ。妻はスキーや水泳などの一人でやるスポーツのほうが好きで、テニスやゴルフなどの球技には興味はなかったようだが、私のテニスへの情熱には反対する余地などなかった。
仕事では酒に淫する日々が続き、私生活ではテニスに夢中になっていた。1年中、雨のとき以外の休みはテニス三昧。日曜日、お互い下手同士だが気の合うクラブの先輩男性と夕方までラリーを続けた翌日、ペンを持つ右手がぶるぶると震えたことも思い出す。右手を酷使しすぎたせいである。あのころコートでお付き合いしていただいた齋藤さん、中村さん、中山さんは今どうしているだろう。年下の石川君とは、いまも賀状の交換が続いているが、30年近く会っていないだろう。
娘が生まれて3歳になったころから、クラブによくバギーに乗せて連れていった。バギーから覗いた小さな裸足が可愛いと、会員の女性たちから嬌声が飛んだりした。暫く打ち合って娘のところに戻ると、誰かからもらったせんべいをくわえていたりしたこともある。
そのクラブを止めざるを得なかったのは、公団の一室が当たって多摩ニュータウンに引っ越しをしたからだ。暫くはバイクで通ったが、やはり距離がありすぎた。実は、テニスクラブのほうでも、動きがあって、会員制からテニススクールに模様替えをしようとしていた。オーナーの態度が会員に対して冷たくなっていたのだ。私は通えなくなって止めたのだが、いずれその時は来たに違いない。
多摩でもテニスクラブを探したが、子供の世話で妻がコートに出ることが難しくなった。そこを押してテニスをしようと思うほど、妻はテニスが好きではなかった。
テニスを止めた。一時的に止めたつもりだったが、それから何度かコートに出たことはあるが、現在はまったくやっていない。先日、屋根裏の倉庫から愛用の4本のラケットを取り出してきた。先ほど述べたドネイのラケットとウィルソンのプロスタッフは昔懐かしい木製である。ロシニョールのマッツ・ビランデル モデル、同じものが2本。こちらの素材はカーボンだろうか。現在のフェイスの大きなモデルへの移行途中の大きさといっていい。4本とも、いまも張られたままのガットは衰えを感じさせない。私は寝室の枕元にお守りのようにこの4本を立てて置いている。
これから観ることができるグランドスラムの大会は、春にフレンチ・オープン、初夏にウィンブルドン、秋にはUSオープンだ。サビーネ・リシキーの姿を見るのが楽しみだが、死ぬまでテニスをやっているだろうと信じていたあの素晴らしい日々はもう還ってこないだろう。