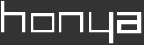閉門即是深山 439
祖父急逝の夜
祖母は、昭和35年4月号の『文藝春秋』に「夫としての菊池寛」と題して、思い出話を書いている。その中には『妻妾の同居』の話もあった。
関東大震災で家を焼かれた女性が、本宅に訪ねて来た。
「あの当時、ちょうど私たちは幼い長女の瑠美子と、親子三人が駒込神明町に住んでいました。私はその前から、主人が芳町の芸者と馴染んでいることを、うすうすは知っていたのですが、ちょうど地震のどさくさまぎれに思いもかけないその女が、主人との間にできた赤ちゃんの男の子一人と、お母さんと女中の四人で、私の家にまいりました。来たというよりはむしろみんなが、着のみ着のまま焼け出されて転がり込んだのです。この人たちはよほどせっぱつまって来たのでしょう。下町のひどい火に追われて、命からがら逃げだして来たのかと思うと、私もつい気の毒になって、いろいろと世話を焼く気になりました。相手にはお金などあるはずもありません。私も主人はいざしらず私のふところは充分ではありません。言わばあるだけのお金をやりくりして、主人の体面をつくろっていたのです。」(中公文庫『菊池寛急逝の夜』)
そのころ、祖母のお腹には、もうすぐに産まれる私の父が居た。父に言わせると、この話などお爺ちゃんの女性に関する逸話のごく一部らしい。「なにせ、お爺ちゃんは、すれ違う女性にはみな声をかけていたからね」と言う。そのようなことが始終この夫婦にあったと思う
ある日、祖母の堪忍袋が切れた!菊池寛は、妻に謝ったが、ただ謝るだけでは祖母は納得しなかった。約束しろと迫る祖母に向かって「六十歳になったら、マジメになります!」と言った。「今後は、浮気はしません」ではなく「六十歳になったら真面目になる」と言ったところがいかにも菊池寛らしい。
しかし祖父は、五十九歳でこの世を去った。この話をしていた時、叔母のナナ子は「お父さんの勝だよね」と笑っていた。
積み重なるこのような話に、生真面目で一徹な性格だった祖母は、夫が六十歳になる前に我慢の限界がきたのだろう。祖父が急逝する半年前に家出をしたのだ。と、言っても菊池寛は、妻が石神井にある別荘にいることは知っていた。ちょうど妻が家出をした次の年の昭和23年2月、新橋にある知人の洋食屋に作家・石川達三等と夕飯を食べに行った祖父は、いつものように豚カツやステーキをたらふく食べたらしい。だが、胃腸を病んで二週間も寝込んでしまった。口に出来る物と言ったらカルピスのみだった。祖父は弱気になった。空気のような存在だった妻が、自分にとってどうしても必要な存在であるのを悟ったようだ。親戚を呼んで「快気祝い」をやろう!あの妻なら見栄も体裁もあるから帰ってくるに違いない!祖父の発案だった。
案の定、快気祝いの前日に妻は帰って来た。親戚ばかりであった。そこには主治医もいたし、ぶらりと立ち寄った文藝春秋の編集者で3代目の社長になった池島信平もいた。また、パージを受けていた祖父の監視役、進駐軍の将校ロバート・ロイドもいた。2歳前の私も居た。
快気祝いも終わり、三々五々別々の部屋で話し込んでいた皆の耳に、私の父を呼ぶ祖父の声が聞こえた。その声が最期の祖父の声となった。