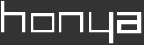閉門即是深山 349
手紙
大正12年9月1日の午前11時58分に、関東大地震は起きた。マグネチュード7.9の大地震である。9月6日付けで祖父・菊池寛は、薄田泣菫(すすきだ きゅうきん/明治10年~昭和20年 『暮笛集』『白羊宮』などで島崎藤村の後を継ぐ浪漫派詩人)宛に1通の手紙を書いている。
「小生は幸にして何の被害もありませんでしたが、もう文藝藝術は、二三年は駄目です。それで大阪へ行かうと思ってゐますから、どうかよろしく。都合に依っては、同志と一緒にサヌキ(讃岐・生まれ故郷)へ帰って、武者小路(実篤)氏にならって百姓をやらうと思ってゐます。とにかく、生活と云ふものゝ真諦が分ったやうな気がします。享楽生活、文化生活と云ったやうなものが、いかに頼みないものかと云ふことが分かりました。自分で働いて、淡々たる簡易生活をやるのが一番いゝと云ふ気がします。とにかく、今の東京はたゞ喰ふことと寝ることが尤も大切なことです。そして、かうした生活に対しては、文藝などゝ云ふものがいかに無用であるかと云ふことを感じます。(後略)」
この手紙、後に友人の作家 里見弴らから反論を招くことになる非常時の時の藝術無能説の一端を示している。祖父は『災後雑感』にも書いた。
「我々文藝家に取って、第一の打撃は、文藝書画などと同じように、無用の贅沢品であることを、マザマザと知ったことである。かねて、そうであることは、知っていたものの、それを、マザマザと見せられたのは、悲しいことだった。
震災に依って、作家の主観が深められ、その為に文藝が深刻になると云ふ人がある。或は然らん。然し、それは作家本位の観察である。我々は、いゝ加減なことを書いては居られないと云ふ気がする。然し、それは作家側の考えである。需要者側の要求する文藝はそうではないだろう、きっと、娯楽本位の通俗的な文藝が流行するだろう。読者は、深刻な現実を逃れんとして娯楽本位な文藝に走るだろうと思ふ。そんな意味でも、文藝の衰頽は来る。
文藝界の衰頽がきても、我々の如きは、年貢の収め時だと思って、甘んじて田園に去るが、気の毒なのは新進作家である。プロレタリア作家もブルジョア作家もあったものではない。」
関東大震災を新型コロナウイルスと変え、文藝と特化した言葉を“小説”、“芝居”、“絵画”、“音楽”、“映画”などのライブと変えてみたら、どう読めるだろうか?大正12年は、1923年である。97年前に文化人たちの経済環境も今とそう変わりが無かったのだ。ライブハウスが無くなれば、若い音楽家たちの表現の場所も無くなる。照明や音響の人たちも路頭に迷う。最初にダメージを受けるのは「人間の証明」なのだろうか!