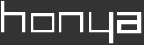閉門即是深山 97
平和憲法の母ごころ
漫画家の巨匠手塚治虫は、1928年、昭和3年に大阪府豊中市で生まれ、1989年、平成元年の2月に胃癌のため享年60歳でその人生の幕を降ろした。
その一生で、氏は『鉄腕アトム』や『ジャングル大帝』、『リボンの騎士』、『火の鳥』などの傑作を遺している。
手塚作品の一貫したテーマは「恐怖と悲劇」、「殺戮と暴力」、「蹂躙と狂気」だったと思う。ようは、「戦争は、絶対にご免だ!」と言っている。
『手塚治虫エッセイ集』を読むと、
私にはただ一つ、これだけは断じて殺されても翻せない主義がある。
それは戦争はご免だということだ。
戦争というのは、兵隊が戦って死んでゆく、という単純なものではありません。
歴史の上で何回も戦争は繰り返され、そのたびに多くの子どもたちが犠牲になってきました。
いまも世界中で沢山の子どもたちが、大人たちの争いの中で傷つき、手足を奪われ、両親や兄弟と引き離され、命も未来も踏みにじられています。
また、手塚治虫氏の著書『ぼくのマンガ人生』には、氏の最後の長編『アドルフに告ぐ』について、
『アドルフに告ぐ』は、ぼくが戦争体験者として第二次大戦の記憶を記録しておきたかったためでもありますが、何よりも、現在の社会不安の根本原因が戦争勃発への不安であり、それにもかかわらず状況がそのほうへ流されていることへの絶望に対する、ぼくのメッセージとして描いてみたかったのです。
もう戦争時代は歴史のかなたです。いまの40歳以下の評論家だと、戦争体験を基礎にした戦争論は書けません。戦時体験は風化していき、大人が子供に伝える戦争の恐怖は、観念化され、説話化されてしまうのではないか。虚心坦懐に記録にとどめたいと思って『アドルフに告ぐ』を描きました。なかでも、全体主義が思想や言論を弾圧して、国家権力による暴力が、正義としてまかり通っていたことを強調しました。
ですから、『アドルフに告ぐ』という作品をお読みになっても、どうして生命の尊厳とか、生命の大切さにつながる話なのだろうとお考えの方もあるかと思いますが、基本的にはぼくのそれまでの戦争体験で、そこに出てくる狂言まわしの日本人がぼくなのです。そういうように、ぼくの作品は一貫して生命というものにこだわっています。
『アドルフに告ぐ』を読んでいらっしゃらない読者のために、この作品のストーリーをかいつまんで書いておく。
昭和11年、1936年、アドルフ・ヒットラー率いるナチス党の隆盛を極めるドイツ。この時代に3人のアドルフがいた。独裁者アドルフ・ヒットラーと、ドイツナチス党員で外交官だった父と日本人の母の間に生まれたアドルフ・カウフマン。そして、ドイツから神戸へと亡命したユダヤ人アドルフ・カミル。この3人のアドルフが、ヒットラーにユダヤ人の血が流れているという機密文章によって翻弄されてゆく物語である。
このマンガで手塚さんは、アドルフ・カウフマンに最後のセリフとして次のように言わせている。
「俺の人生は一体なんだったんだろう。あちこちの国で正義というやつにつきあって、そして何もかも失った…肉親も…友情も…おれ自身まで…おれはおろかな人間なんだ。だが、おろかな人間はゴマンといるから国は正義をふりかざせるんだろうな」と。
ヒットラー率いるナチス党も「正義」の旗印の下に戦争を仕掛け、ユダヤ人を迫害した。あれが「正義」か、否かは別にして、「正義」とは、いったい何ぞや?を手塚さんは、問いかけている。権力・独裁による「正義」と国民の目線による「正義」は、自ずから違う。しかし、その「正義」を振りかざしたアドルフ・ヒットラー率いるナチス党も国民が選出した「党」なのである。
だから「現在は昔と違う!」と言いながら「平和で母のこころを持つ我らの素晴らしい日本国憲法」を穿った解釈の基に振りかざす「正義」には、気をつけねばならない。いつの世にも、このような狂った「正義」を振りかざす輩が生まれてくるのを我々は、歴史の中で見て来たはずなのだから。
しかし、現首相も代議士も官僚たちも手塚治虫氏のマンガを読んできてるはずなのになぁ!読んだことは、読んだが学ばなかったのだろうか。
『アドルフに告ぐ』は、劇団のスタジオライフで芝居になり明日、8月22日(土)と23日(日)に梅田芸術劇場シアター・ドラマシティで公演される。残念だが、東京公演は終わってしまった。
舞台の最後はあのセリフである。
「俺の人生は一体なんだったんだろう。あちこちの国で正義というやつにつきあって、そして何もかも失った…肉親も…友情も…おれ自身まで…おれはおろかな人間なんだ。だが、おろかな人間はゴマンといるから国は正義をふりかざせるんだろうな」
こんなことを私は後で、言いたくはない!