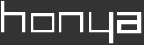閉門即是深山 252
唯我独尊
駅前のコーヒー店で並んでいたら声をかけられた。声だったのか、肩をトントンと叩かれたのかは、判らない。忘れた。この夏の暑さで、老いぼれた脳ミソが水状化して溶けだしたようだ。ドラムの自己練習の後、水分を補給するためにと店に入ったところだった。今朝も時間潰しに入った。
朝は、喫煙ルームに老人が集まる。次第に、仲間になる。大きな声を出す。若者や女性に敬遠される。だから老いた爺と、デカイ声の婆が寄り添うようになる。歯が抜けようと、口が臭かろうと、椅子に胡坐をかこうと、構わない。歯が煙草のヤニで黄ばんでいようが、猛暑でも長袖を着ようと、病の話・病院の話、看護師の女性を「あの姉ちゃん」と呼び、抜けた歯でヒワイにヘヘ!と笑おうと構わない。悲劇なのは、その店で働く女性たちで、クソ爺から「ちょいと姉ちゃん」と呼ばれている。しかし、文句も言えないだろう。私を除けば、土日を除くほとんど毎日、行き場を失ったその老人たちが300円とポイントカードを握りしめて来るのだから。その店の店員にとって、土日だけが安息の日であろう。しかし、老人は朝しか来ない。老人は、日が高くなると家にじっとしているのかも知れない。と言っている私も上位の老人であるし、ポイントカードと300円を握りしめて入る。今日は、水分補給だからアイスコーヒーを注文しようと思っていた。
私に声をかけてきた爺さんが、一瞬誰だか判らなかった。真っ白の髪、白のスニーカー、白いパンツに麻のシャツの袖をまくっている。お洒落な爺さん。あっ、以前何回も海外旅行に一緒に行った親友である。私の前に割り込み彼は、カウンターに「ソフト」と言っている。私の後ろにも大ぜいの人が並んでいるのだ。私は、後ろにいる人に頭を下げ「ソフトクリームを2つね」と二人分払った。アイスコーヒーとソフトとは、後ろに待つ人の手前言えない。これなら最初から二人分を買いに来たと主張も出来るはず、と爺なりに咄嗟の判断をしたのだが、後ろで待つ若者は、臭い物でも見るように嫌な顔をした。
席に座った。彼とは、2ヶ月前にも横浜で会った。以前より眼が窪んでいる。「目が悪くなっちゃってね、階段なんか怖くて降りられないんだ。エレベータだよ」席に座りながら嘆いている。2時間近く話したが、互いに耳も悪く、滑舌も悪くなっているから殆んど通じない。ただ彼が「『70歳になってわかること』は、とても頷けた。中の絵にも癒された」と言ってくれたことは判った。この夏、家人が文芸社から出版した本のことだ。その帯には「若い人こそメッセージを受け取って、素敵な人生を目指して欲しいです」との著者菊池未生の言葉と、「生き方は人それぞれ。ちょっと耳を傾けてほしい。未来を充実させるための、気づきとヒントがつまった一冊。」と書かれてある。