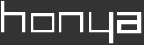閉門即是深山 34
ぎんざ♫ ぎんざ♪ 銀座~!
ある作家の40周年記念会の一次会が終わった。
みなさ~ん! 二次会は、木屋の上でおこないま~す! 時間のあるひとは、そちらに行ってくださ~い! 雨ですから滑らないようにお願いしま~す!
若い女性編集者の声が、酒焼けした喋り過ぎた濁声の間をぬって聞こえてきた。「滑らないように」というところは、我々老人引退組み編集者をちらっと見ながら言ったようである。“うどん屋木屋”といえば編集者たちに通じる。若き女性幹事が生まれるずっと以前から通っていた店で、文壇バーのひとつであった。「そんなとこお前さんがオムツをしているときから行ってるゾ!」とからかうようにOBの声が聞こえた。
その店は、銀座7丁目、並木通りに面したビルの2階にある。一次会場から歩いて10分くらいだろう。この日、私はとことんこの作家の会に付き合う覚悟で来ていた。7、8年ぶりの夜遊びである。現役時代は、毎日のように、それも始発が出る時間帯まで、作家と付き合っていた。夜の銀座は、目を瞑っていても歩けたし、携帯の登録もほとんどが銀座のバーやクラブのものだった。
年は取りたくない! 最近では、土日の昼間の銀座ばかりで、健康的である。家から地下鉄に乗り3つ目に銀座の駅がある。私の中では、映画の街と化してしまった。現役時代は、タクシーでも一時間もかかった街なのだが…。
木屋の2階の店は、39年ほど前に亡くなった梶山季之氏が可愛がっていたママの店だった。梶さんの作品といえば産業スパイ小説『黒の試走車』や『赤いダイヤ』が挙げられる。推理小説、時代小説、風俗小説と多岐にわたってヒットを飛ばした流行作家だった。その梶さんが、可愛がり、愛したママは、さぞ昔は可愛かっただろう面影を残すが、怖い!「夏樹!何してやがったんダ~!」と言われそうで、怖い。当然というか、そうだろうというか、私よりずっと年上の女性だから、怖い!
先生は、タクシーに乗ったようだ。また、三々五々タクシーを停めて編集者たちは、相乗りしているのが見える。私は、そぼ降る雨の中、傘をさした。最近は、自分の車を使って動くことが多くなった。久しぶりの夜の銀座を歩くのもオツなものだ。前の方にF社の女親分と、引退した編集者が肩を並べ話し歩きをしている。こんな夜は、ひとり歩きがいい。大きな歩道橋で昭和通りを渡って、中央通りの信号を越し、木屋に向かった。忘れてはいない。目を瞑っては、歩けないものの。目を開ければ判った。エレベータで前のふたりに追いついた。
店に入ると、タクシー組より早く着いたようだった。
この店は、ほとんどカウンターで、カウンターが馬蹄型になっている。ボックス席がひとつ。昔は、夜というか、朝方タクシー待ちに皆が集まってきた店だ。他の文壇クラブや文壇バーよりも遅くに店を閉める。だから、客も安心して、もう一杯と思い、来るのだろう。この店の近所に、小説家や小説の編集者がよく使うバーが多かった。いわゆる文壇バーである。今は、もう無くなってしまったが「葡萄屋」「眉」もこの近くにあった。「眉」を閉店するとき、「眉」のママに一輪のバラを持ってお礼に行ったことを思い出す。
私が若い時分「眉」のママにはお世話になった。変な意味ではなく大人の礼儀や遊び方を教わった。スパルタ教育だった。「眉」無き後、チーママが、木屋の向かいの有名な“おでんや”の入るビルの上で「小眉」を開いたが、その店も今はもう無い。「眉」では、毎晩のようにお偉い作家たちで寿司詰めの状態だった。奥の席に行こうものなら、若かった私なぞ、各テーブルを米突きバッタのようにして入って行かねば席に着けなかった。
「葡萄屋」には、書店の紀伊國屋の社長田辺さんや講談社の社長、小学館の社長のお顔をよく見た。作家の先生方も沢山来られていた。社長さんたちに「おい、菊池くん!こっちに来いよ、一緒に飲もう」と誘われた。社会の勉強のお時間であった。
電車ももう無くなるころ、二次会は、お開きになった。タクシーで何万も払わねばならないOBたちは、帰っていった。そして、三次会。タクシー代は、この年で痛いけれど、2千円くらいだろうし、二次会の費用は、出版社各社の割り勘になったから、歩いて50歩くらいの三次会場に向かった。そのビルは、大昔来たことがあった。誰に誘われたのだろう。ホステスの中にひとりオカマの娘がいたのを鮮明に覚えている。
店に入っていくと胸元も露わな真っ赤なスパンコールの人魚のようなドレスママが、OBたち一人一人に「キャーッ、○○ちゃん、久しぶり~!」と抱きついてきた。閉口する。実は、何年か前にある出版社の編集長と結婚した女性であるのだ。結婚式にも出た。彼も今日一緒で、席に座っている。もちろん、その娘は、結婚前からの皆の知り合いで、夜中のドンチャン騒ぎの仲間だった。歌いくるい、肌着も露わに、店のソファーで跳ね飛んでいた娘だった。しかし、今は、人妻で、亭主もそこにいる。昔のようにキャーッと言って抱き合うわけにもいかない。もちろん、こちらも爺で、娘のようなものだから何も感じていないのだが、亭主の前で抱きつかれるのには、照れも含め困ってしまう。これは、介護の一環だと思ってやらせてはいるが、困ったものだ。
カウンターに座って、仲の良かったOB編集者と話していたら、亭主とママのひそひそ話が聞こえてきた。やはり、亭主が焼きもちを焼いているらしい。妻ママの声が聞こえた。
私のご商売よ!って。